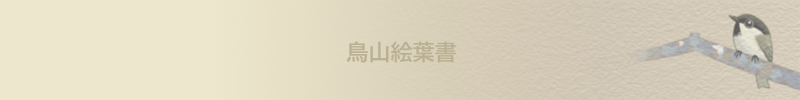野外手帳
-2020年8月
またしても夜善光寺
代わり映えしないですけど、またも夜善光寺です。雲間に輝くのは月齢9の月。

光る石畳の仲見世通り。

仁王門付近。

大本願前。

中央通り。

礒五郎前。

2020年9月なかごろ記
再び夜ポタ
こうしてみると、夜限定ですけど、長野市中心街は結構フォトジェニックかもしれません。

全く人は歩いていませんけどね…。

2020年9月なかごろ記
昼ポタ畦道
今年の夏は自転車に乗るには暑すぎます。でもたまには昼間にもってことで、ミニベロにまたがり家を出ました。日陰に入るとほっとします。

やっぱり遠くへ行く元気はなくて、近所を一回りくらいがせいぜいです。いつもの畦道。

夏の終りに咲くニラの花には、いろいろな虫が吸蜜に来ます。この日見つけたのはトモンハナバチ。

2020年9月はじめ記
夜狐
帰宅途中、車の中からキツネを見ました。夜にキツネらしい声を自宅で聞くことは何度かありましたが、こうしてはっきり姿を夜に見られることは珍しいです。

車のライトに照らされても特に動じる様子はなく、、こちらをじっと見ていました。慌ててスマホを取り出したものの、すでに空き地の草むらへ消えていこうとする姿しか撮れませんでした。。
2020年9月はじめ記
夜ポタ善光寺
暑さを避けるために自転車に乗るのは夜が多くなっています。そして夜だとどうしても街に向かってしまいます。駅方面へ行くのなら、途中、善光寺には寄らざるを得ません。これは善光寺仲見世のスタバ前。

善光寺というのは面白いところで、遅い時間帯でも境内や参道を誰かしらが歩いています。

門前で八幡屋礒五郎の軽トラを見つけたので、その前で記念写真。
2020年9月はじめ記
上空にハチクマの森

ゴゼンタチバナが赤い実をつけていた、8月中旬の某所です。

歩き始めはダケカンバの森。コガラ、ルリビタキ、メボソムシクイ、ウグイス、クロジなど。

ふと見上げれば2羽のハチクマ。これでも大トリミングです。

ほぼ等倍近くまで切り出してみると、画像からもハチクマだとはっきりわかります。まもなく渡りの季節ですねぇ。

昨シーズンはここでたくさんのアサギマダラに会えましたが、今回は1頭だけ。移動していくチョウなのでタイミングが合わないとこんなものなんでしょう。

ここでとても多いのがヒメキマダラヒカゲです。

足元にはキノコがたくさんありました。とても全部は写真に撮りきれないくらい。

全部未同定ですけど見ているだけで楽しいです。

そして最後に見つけたのはシャクジョウソウたぶん。初めて見ました。右は同じく腐生植物のオニノヤガラの終わりかけです。

仕事と介護の合間を縫っての森歩きでしたが、いろいろな生き物を見ることができて楽しく過ごせました。限られた時間の中でこうした機会が得られるのは長野に住んでいるからで、その幸せを改めて思います。
2020年9月はじめ記
湿原周りのチョウはやや不作

8月中旬の某湿原です。この木道を見ればわかる人にはどこなのかおわかりでしょうけど。花を見ると、この湿原ではすでに秋が始まっていることがわかります。

ここではいつも見られるホオジロ。

今回の主な目的は蝶でしたが、数的にも種類的にも今ひとつでした。これはウラギンヒョウモン。だいぶ翅が痛んできています。

こちらはギンボシだと思います。もっと他にもヒョウモン系がたくさんいると思ったんですけど、この2種だけでした。

クジャクチョウ。1頭だけ見ました。

比較的たくさんいたオオチャバネセセリ。

未同定蛾。ちょっと悔しい。

暑さを避けるアキアカネ。

いつもなんだかロマンを勝手に感じてしまうキスゲフクレアブラムシたち。そのロマンってのはうまく説明できないんですけど、彼らはどこから来てどこへ行くのかって感じです。

というわけでやや消化不良な湿原散策でした。
2020年9月はじめ記
お盆の善光寺

誰も帰ってこない寂しいお盆だったので、暇な夜に善光寺までポタリングに出かけました。

そんなに遅い時間帯ではありませんでしたが、ほとんど人影はなく、ひっそりとした夜の善光寺でした。

2020年8月おわり記
8月中旬の道ばたの森

8月中旬の道ばたの森は夏から晩夏の花々に彩られた美しい森でした。

キンミズヒキはもう完全に秋の花のイメージです。

コバノフユイチゴとバライチゴ。

キノコは未同定。最近はもうキノコの同定は完全にあきらめています。

ホタルガは初めて見ました。蛾初心者なので、初見の種には事欠きません。図鑑でしか見たことがない種類が目の前に現れるのは、やっぱりちょっと興奮します。
シロシタホタルガに訂正です。(2021年7月)

もっと近くで見られたのですがカメラが間に合わず、これはかなり離れたところから撮った1枚です。
下の蛾はよくわかりません。シャクガの仲間だとは思いますけれど。

この森ではゴイシシジミにほぼ確実に会えるのが嬉しいです。ひらひら舞うとき、翅裏の白だけがパッパと光るように見えるのがとても印象的です。そして止まるととってもかわいい。

肢に鮮やかな色を見せるバッタを見ました。ミカドフキバッタだと思われます。

アオイトトンボとカワトンボの仲間。カワトンボの個体数は、以前ここではかなり多かったのですが、倒木以後はあまり見かけなくなっていました。無事だったか!って感じです。

首?にダニっぽいものをつけたシリアゲ。カメムシをとらえたアブ。いずれも未同定。↓

アカハナカミキリとウスバカゲロウ。↑

もともと他の人に会うことはほとんどないこの森ですが、大量の倒木でこの森を歩く数少ない人がさらに減っていると思われます。というわけでかなり藪っぽくなってきていて、刈払いが入らないと来季はもう歩けなくなるかもしれません。
2020年8月おわり記
夕暮れ時のポタリング

いつもの畦道がちょっと特別な風景に。
2020年8月おわり記
美しい小径

8月上旬の某高原です。緩いカーブが印象的な小径を歩きました。鳥的には不調でした。唯一視認できたアカゲラの若いのです。

鱗翅ではまずモンクロシャチホコ。私が図鑑なしでもわかる数少ない蛾の一つです。

続いてヒトリガ。これも図鑑なしでもいけます。

これは図鑑を見なければ無理でした。ヨコジマナミシャクみたいです。標本写真を見ても腹部をこうやって持ち上げているのがありました。これが標準的な姿勢なのでしょうか。

よくわからない方々。すみません。

蝶。ミドリシジミと思われます。このあたりもまだ全部同じように見えるので、修行が足りないです。

その他の蝶。

ハバチイモは未同定。

植物はオニノヤガラその他。

ウバユリを刈り残しているのは管理者の趣味なんでしょう。個人的にはどうかと思いますが、印象的な風景になっていたことは確かです。

2020年8月おわり記
湿原でキヒゲアシブトとヘリグロとモモブト
ツリフネソウが木道に揺れる小さな湿原を歩きました。ここは初めての場所です。

鳥は木道に一瞬姿を表したクロツグミ。そのほか、ウグイス、アオジ、モズなど。木道上にたくさんいたのはヒメギス。

環境が良くないといないという、イナゴモドキも見ることができました。っていうかイナゴモドキでいいんですよね?直翅はやっぱり難しいです。

ここの湿原はドクゼリでしょうか、それがすごく多いのが印象的でした。

その花にたくさんのアブが集まって吸蜜していました。あとで調べてみると、これはキヒゲアシブトハナアブという種類で、これも先程のイナゴモドキと同じく、自然環境が良好に保たれている場所でないと見られないとのことです。
この湿原の周囲は開発が進んでいて、その中にぽつんと残されているという感じなのですが、湿原の中は自然が保たれているということが言えそうです。

ミゾソバが咲き始めていました。

この湿原で見た蝶と蛾。まずはヘリグロチャバネセセリ。

以前、ヘリグロかスジグロかで迷った画像があったのですが、こうして比べてみると、翅の縁がスジグロは淡いオレンジ色で、ヘリグロはそれより白っぽいという違いがよくわかります。
続いてアトヘリアオシャク。

初めて見ました。鳥はなかなか新しい種類を見るということがなくなってしまっていますが、昆虫は初見がたくさんで楽しいです。
そしてこのイモは2回めです。

確かこれを教えてもらったときに初めてtwitterの集合知ってすごいって思ったのでした。このサイトを検索してみると2012年の8月「ヒヨドリバナ咲く森(キイロモモブトハバチについて追記)」が当時の記事です。というわけで8年ぶりのキイロモモブトハバチでした。
2020年8月おわり記
高原蛾探とアオコシホソハバチ
「高原探蝶記」の続きです。今回は主にガ。

上は局所的にはとても多かったキンモンガ。名前がすんなりわかったのはこのくらいで、以下は同定に苦労しました。まずはシロオビクロナミシャクでしょうか。このガは変異が大きすぎてもう何が何だか私には無理です。雰囲気で同定。

続いてウスグロアツバと考えてみたガ。

そして写真を撮ったときにはよくわからなかったのですが、PCで見てわかったヒョウモンエダシャク。ストロボを焚いても暗かったので、画像処理でだいぶ明るくしてあります。

そしてそして、こんなのにも出会ってしまいました。鈴には全く無反応。

最後に見たハチは水色の差し色が最高に美しく(写真ではあまり青く写っていませんが)、一気にファンになりました。アオコシホソハバチみたいです。検索してみてもどんなハバチなのかさっぱり情報がつかめません。

というわけで、クマに遭ってしまいましたが、無事帰還できました。今年は熊の出没情報が多く、また事故も起きています。気をつけなければ。
2020年8月おわり記
高原探蝶記

8月上旬、キノコがポコポコ生えている某高原の探蝶記録です。ちなみに鳥は、カケス、ウグイス、センダイムシクイ、モズ、ホオジロを確認しました。目当てはアサギマダラです。ここは自分の中では「アサギマダラを確実に見られる場所」のひとつなのですが、年によってはほとんど見られないこともあります。この日は歩き始めて数分で出会うことができました。

あまり簡単に見ることができるとありがたみが薄れてしまう…なんてことを言ってはいけませんね。きっとそのうち罰が当たります。

ヒョウモンチョウの仲間も、全然見かけることができないシーズンがありました。今年はぜいたくな眺めです。

一番多いのはオオウラギンスジヒョウモンです。

ちょっと小さめなのはウラギンヒョウモン。

ミドリヒョウモンはオオウラギンスジに次いで多い印象です。

それからヒメキマダラヒカゲ。このチョウはやたら多い場所とそうでない場所との差がこの高原でも激しい印象です。ここでは少なめ。よく見ると、この蝶も美しいですねぇ。

なかなか翅表を撮らせてもらえないクジャクチョウ。

トラフシジミ。

その他、サカハチ、クロヒカゲ、モンキ、スジグロ。

続きはこちら。
2020年8月おわり記
庭のトモンハナバチ
庭のブルーサルビアが咲くのを見計らうかのようにやってくるトモンハナバチ。
twitterで教えてもらいましたが、どこでも見られるハチではないとのことです。検索してみると生息地は局所的で、わざわざこのハチを見に行ったというブログ記事に行き当たります。

写真の個体は紋が2列 ×6紋なのでオスですね。ブルーサルビアの蜜が好みなのか、よくぞここを探り当ててやってくるものだと思います。そしてこの写真を撮ってから1週間後の今日は、すでに姿がありません。もうここには十分な蜜がなくなって、違うところへ行ったということなのでしょう。

2020年8月なかごろ記
道ばたの森をこれからも歩く
「キンモンガそしてアミメリンガ」の続きです。 鳥はウグイス、ノジコ、アカゲラ、カケスを確認。カケスは小さな群れで林道を横切っていきました。

環境の変化で、この場所での数が減っているように感じて気になっている上のアオイトトンボ(もしくはオオアオイトトンボ)。この日もその印象は変わりませんでした。あとカワトンボの仲間もかなりいたと思うのですが、その姿を今回も見ることができませんでした。
きれいなコウチュウがいました。レンズを向けるとすぐに飛び立ってしまい、彼もなかなか敏感です。

オオスジコガネではないかと思います。
次のは同定していません。雰囲気的にハバチのイモだと考えましたが腹脚の数は数えてません。

タマゴタケ、見つけると嬉しいですが、実はまだ食べたことがありません。間違いないと思うのですが、自分ひとりの判断ではやっぱり抵抗があります。

最後はコバノフユイチゴ。

大規模な倒木で環境が変わり、この「道ばたの森」エリアに行く気分にはなれないでいました。もうあの景色を見ることはできないのかという悲しさが先に立ってしまうのです。
でもこうして歩いてみると新たな発見があり、気づいたり思ったりすることも多くて、やっぱりこれからも歩いていこうと思った一日でした。
2020年8月なかごろ記
キンモンガそしてアミメリンガ
8月上旬、道ばたの森に行きました。
いよいよキンモンガ登場です。

この辺りでは、とても多くのキンモンガを見たことがあります。この日の数はそれほどでもありませんでしたが、季節の移り変わりを、見られるガの種類の変化で感じるってのも、なかなかいいものです。
そしてこの日初めて見たガ。こんなガもいるんだー!とその美しさに感動しました。家に帰って「日本の蛾」で調べると、アミメリンガだとわかりました。

次のガは前回も見たガで、自力では同定できなかった種類です。twitterで聞いてみるとすぐに答えが帰ってきました。世の中にはすごい人がたくさんいるってことがよくわかります。ちなみに「日本の蛾」には載っていませんでした。というわけで、複雑な模様がすばらしいクワヒメハマキです。

非常に敏感でなかなか撮れないシラフシロオビナミシャク。翅の縁に白い部分がないとシロオビクロナミシャクになります。なぜシラフシロオビクロナミシャクではなくてシラフシロオビナミシャクなのか、いつも気になってしまいます。

逆光で少しかっこよく撮れました。
さていつも迷うマダラエダシャクの仲間。前翅の灰色紋の中に輪が見えるので、ユウマダラエダシャクでないことはわかります。

チョウは3種見ました。写真に撮れなかったゴイシシジミ。下のはクモガタヒョウモンだと思います。この場所ではあまり見ることのないチョウです。

そして毎度おなじみスジボソシロチョウもしくはヤマト。

続きはこちら。
2020年8月なかごろ記
戸隠森林植物園の夏の面々
戸隠森林植物園の花とチョウの続きです。鳥はあまり見ることができませんでした。葉が茂っているのでそもそも視認は厳しいですし、繁殖が終わってきているのでさえずっている種類も少ないです。この声はなんだろう?と、姿をなんとか探して見ることができた鳥はコサメビタキ(左)でした。春に聞くさえずりとはかなり違った声でした。

幼鳥の声は成鳥とは少し違うので、この時季は悩むことが多くなります。上の画像右はシジュウカラの若いのです。鳥はこのコサメビタキとシジュウカラ以外に、コガラ、ヒガラ、エナガ、ウグイス、ミソサザイ、ホトトギス、カイツブリを確認しました。
カイツブリも幼鳥の姿が。

親鳥からもらっていたのはトンボに見えます。

「エンジェルポーズ」も見せてくれて、かわいさ爆発です。

続いてヤマアカガエル。

ヨツスジハナカミキリ。

アキアカネです。

本当に久しぶりの戸隠でした。この夏にもう一度くらい行けるといいなと思っています。
2020年8月なかごろ記
戸隠森林植物園の夏のチョウ
戸隠森林植物園の花の続きでチョウです。まずはアサギマダラ。今回は例年より多く見かける感じがしました。とはいっても継続的に観察しているわけではないので、単なる印象です。渡りに行き当たるかどうかでも観察できる個体数は全然違ってくるでしょうし。

それにしてもほれぼれするような美しさです。渡りをするというロマンも加わって、もうたまりません。

ヒョウモンのレストランとなっていたヨツバヒヨドリ。集まっていたのはミドリヒョウモン、オオウラギンスジヒョウモンです。

ウラギンヒョウモンも何個体か見ることができました。花はタチアザミかな。

あまり見ることのないメスグロヒョウモンも登場、、嬉しかったです。

木道上にキタテハ。

葉の上にヒメキマダラヒカゲ。

敏感きわまりないクロヒカゲ。普通のマクロレンズでは撮れる気がしません。今回のチョウ写真は、すべて鳥撮り装備のサンヨン×1.4で撮ってます。

タテハチョウ科からもう1種、サカハチチョウ。翅裏の模様がすごすぎます。

一番の目当てだったのはミヤマカラスアゲハです。近くでは撮れなかったので、かなりトリミングしてあります。現地ではミヤマだと思い込んでいましたが、画像を確認するとミヤマではなくて、カラスアゲハのようです。

いくつか撮ってみればミヤマも撮れたのかもしれません。
ミヤマカラスアゲハは確認できませんでしたが、ミヤマカラスシジミと思われる個体は見ました。この仲間の翅の模様も覚えられない…。写真を撮ってきて図鑑と合わせる、その作業の繰り返しです。

続いてシロチョウ科。スジグロシロチョウ。ヤマトとの識別は自信がありません。花は咲き始めているミゾソバ。

スジボソヤマキチョウ。よくみるとクモが写っています。獲物としては大きすぎですね。

ガも少し。ヒゲナガキバガの一種と未同定のたぶんシャクガの仲間。

毎度おなじみ、イカリモンガ。ガをもっと見ることができると思っていましたが、やや空振り気味でした。

2020年8月なかごろ記
戸隠森林植物園の夏の花
8月上旬の戸隠森林植物園です。
3月にスノーシューをつけて入ったきりで、今季は新型コロナ的に行くのをやめておこうと思っていました。特に、世の中に外出自粛の嵐が吹き荒れていた4月、5月は鳥を見るには一番のシーズンでしたが、戸隠には行かずに過ごしました。でも、外出することへの風当たりはだいぶおさまりましたし、特に観光客的には見どころのない8月は、お盆前なら人出が少ないと見込んで出かけてみました。予想通り、駐車場には数台の車しかありませんでした。

木道は一部撤去されていて、例年通りのコース取りはできませんでした。今回のねらいは主にチョウで、そのスポットの一つは上の画像の木道が撤去された先にあったので、その点はとても残念でした。

ノブキの白い花があちこちに咲いていました。下のズダヤクシュの花には間に合わず、写真は実をつけた姿です。

晩夏の花のイメージ、キツリフネはアカアシカスミカメ付き。

エゾアジサイはまだ健在。

9月の花のイメージがあるレイジンソウはこれからというところでした。例によってアズマかどうかはわかりません。

ウバユリとシキンカラマツにはちょっと遅かったです。(下画像の左上と下)

タマガワホトトギスは完全におしまい。見たかった。

ナルコユリも実をつけていました。

赤い実の中からはトチバニンジンをアップ。他の赤いのがよくわからないということでもあります。

さてあちこちに咲いていたのはヨツバヒヨドリ。というわけで、次回はチョウの紹介です。

2020年8月なかごろ記
午後4時からのポタリング
自転車にあまり乗れていなかったのでぐるっとひと回りのつもりが、ついつい千曲川まで。橋の向こうには梅雨明けを告げる入道雲が見えていました。

帰りにレモンとはちみつ贅沢搾りを買ってきました。
2020年8月なかごろ記
8月のムシなど(道ばたの森)
8月初旬の道ばたの森、チョウ、ガに続いて、その他のムシなど編です。
初めて見たこの昆虫。ナナフシの仲間だとわかりましたが、画像と図鑑を合わせてみて、ヤスマツトビナナフシと判明。数は少なめみたいです。

トゲカメムシでいいと思います。

キイロカミキリモドキでしょうか。

ツマジロハバチ。

さて、気になるのはこのアオイトトンボもしくはオオアオイトトンボです。この森の大規模な倒木によって環境が変わり、かなり明るくなり、生き物の生息状況がどう変わるのかと思っていました。このイトトンボは明らかに数を減らしています。

数歩歩くたびに近くの枝から何匹もが飛び立つという感じでしたが、今回はほんの数個体しか見ることができませんでした。
この森では何度か見かけているキイロホソガガンボと思われる昆虫。

交尾しているアブの仲間。未同定。

ハバチ幼虫。

シャクガ幼虫。

昆虫を離れまして、ザトウムシの仲間。何かを食べてます。

アシナガサラグモだと思います。美しいなぁ。手前がメス、向こうがオス。

「鳥山絵葉書」なので、鳥も。アオジ幼鳥と成鳥。

その他、ノジコ、ウグイス、イカル、コガラ、シジュウカラ。そしてマガモ。越夏個体ですよね。

最後にキノコを貼っておしまいです。ハナビラタケは食べられるらしいです。でもやっぱりキノコは詳しい誰かに後押ししてもらわないと、手を出せないですね。

2020年8月なかごろ記
8月のガ(道ばたの森)
8月初旬の道ばたの森、ガ編です。
まずはトンボエダシャク。

非常に敏感で、なかなか撮らせてもらえない、シラフシロオビナミシャク。

ヒゲナガキバガの仲間。

毎度おなじみ、チョウとガの区別にあまり意味がないことを教えるイカリモンガ。ストロボを使うと眼が光ってしまいます。

同定をあきらめた人たち。ハマキガの仲間でしょうか。わかるようになりたいです。左上のガは、twitterで聞いて正体が判明しましたが、そのことについては後日。

これもあきらめ組。どうせ趣味で撮っているだけなので、地味目のガは撮らないようにすれば同定で苦労することもないのです。でも渋い美しさがあるなあ…!などと思ってついつい撮ってしまうのです。

そして最後に出たのはこのガ。これは調べやすくて、ヒョウモンエダシャクとすぐわかりました。初めて見ました。

2020年8月なかごろ記
8月のチョウ(道ばたの森)
8月初旬の道ばたの森です。緑が気持ちいい森です。でも気持ちがいいのはこの入口辺りだけで、少し進むと倒木地獄です。

ノブキ、ツリフネソウ、オカトラノオ、ゲンノショウコの季節になりました。

これはヤマキチョウでしょうか。スジボソとの区別に自信がありません。

ヤマキチョウは図鑑によると結構珍しいらしいので、そうだとしたらラッキーです。こっち↓はスジボソヤマキチョウでいいと思います。

よく見かけるオオウラギンスジヒョウモン。

前にも記事にしましたが(自由研究「ヒョウモンは難しい」)、オオウラギンスジヒョウモン、ウラギンスジヒョウモン、ウラギンヒョウモン、オオウラギンヒョウモンの命名の紛らわしさは、初心者には混乱の元です。

↑ミドリヒョウモンはわかりやすくて好きです。↓これはスジグロシロチョウかヤマトスジグロシロチョウのどちらかだと思います。識別は自信がないです。

下のセセリも私には難しくてですね。翅の表が見えなかったので、スジグロチャバネセセリかヘリグロチャバネセセリかがわかりません。

翅の縁が、スジグロは淡いオレンジ色で、ヘリグロはそれより白っぽいとのことです。それをそのまま受け止めるとスジグロのように見えます。
【追記】twitterでスジグロチャバネセセリと教えていただきました。数の少ない珍しいチョウだとのことで、改めて感動しました。
ゴイシシジミはこの森に晩夏を告げるチョウです。まだ数は少なめでした。飛び方に特徴があって、飛翔を見てもわかるようになってきました。すごくかわいいけどイモは肉食系なのですよね。成虫も花の蜜は吸わないで、アブラムシが頼りらしいです。

チョウの最後はヒメウラナミジャノメです。

つづきはこちら。
2020年8月なかごろ記
名前がわからなかった蛾
ここから8月の記事になります。晴れ間を見つけて某湿原の木道を歩きました。

だいぶ木が生えてきていて、森林化への過程をたどっている湿原なのだと思います。でも10万年以上前から存在している湿原なのだとか。

チョウに期待して歩いたのですが、アサギマダラを1頭とひらひら飛んでいたなんとかヒョウモンを同じく1頭、あと別の場所でジャノメチョウを数頭見ただけでした。

その代わり初めて見られたガが2種。1つ目はこのキベリシロナミシャクです。葉の裏側に止まるので撮影が難しいのですが、なんとか撮ることができました。美しいガです。

2種目。これは同定できませんでした。ケンモンの仲間?と思いながら、買ったばかりの「日本の蛾」図鑑で調べてみてもわからず、web図鑑を見ているうちにフトメイガの仲間なんだろうかと検討をつけてみたものの、やっぱりわからず。

そこでtwitterで聞いてみると数分で答えが返ってきました。本当に世の中にはすごい人達がいるものです。
マメキシタバ、もしくはコシロシタバではないかとのことでした。シタバガの仲間とは盲点でした。自力ではたどり着けないのは、まだまだ勉強不足、経験不足ということです。

鳥はオオルリ、ノジコ、シジュウカラ、ウグイス、コゲラなど。

見かけた黄色い花の正体はクサレダマと判明しました。この名前の由来はなんでしょう。右のオレンジのはコオニユリだと思います。
2020年8月はじめ記