自由研究
オオダイサギについての考察
白鷺(シラサギ)と呼ばれる種類は、ダイサギ、チュウサギ、コサギの3種であることは、鳥を知っている人には周知の事実。アマサギ冬羽やクロサギ白色型、カラシラサギを加えることもできますけど。
いずれにしても一般の方(?)を相手に、「シラサギっていう名前の鳥はいないんですよー」などと、知ったかぶりをすることができます。
同じイヤらしさとして、「キツツキっていう名前の鳥はいないんですよー」「カラスっていう名前の鳥はいないんですよー」などの用例を挙げることができるのは、言うまでもありません。

シラサギ3種を区別するようになったのは江戸時代からなのだそうです。
そしてときどき話題になるのは(ならないかもしれませんが)、大鷺は「ダイサギ」と「大」を音読み、中鷺も「チュウサギ」で「中」を音読みするのに、なぜ小鷺の小は「ショウサギ」ではなく、訓読みで「コサギ」なのかということです。
同じ法則は、ダイシャクシギ(大杓鷸)、チュウシャクシギ(中杓鷸)、コシャクシギ(小杓鷸)にも当てはまります。こちらも「ショウ」ではなく「コ」です(下イラストは上から大中小です)。

「小」を「コ」と訓読みする鳥は、コガモ(小鴨)、コゲラ(小啄木鳥)、コガラ(小雀)、コルリ(小瑠璃)など、おなじみの鳥だけでもすらすらと挙げられます。
ある種名に「コ」をつけると別種になる例もたくさんあります。コサメビタキ、コアジサシ、コキアシシギ、コチョウゲンボウ、コスズガモ、コアカゲラ、コベニヒワ、コムクドリ(下イラスト)などなど。
一応小型の「コ」ということになるんでしょう。
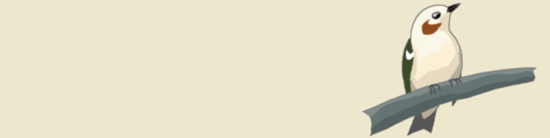
逆に「小」を「ショウ」と音読みする例はほとんどなく、知る限りショウドウツバメ(小洞燕)だけ。ショウドウツバメはおそらく巣穴を掘るところから来た名前で、小さいドウツバメという意味ではないです。
こう見てくると、コサギという読み方は妥当かなと思うわけです。
次に「大」について考えてみます。
図鑑をぱらぱらめくると「オオ」と訓読みするケースがほとんどです。
オオソリハシシギ(下イラスト)、オオアカゲラ、オオコノハズク、オオバン、オオセッカなど。必ずしも大きいわけではないですが、「大型」のオオですよね。

ダイサギは大型のサギなので、「オオサギ」の方が自然な呼び方と言えるのですが、安土桃山時代からの由緒ある名前らしいし、いいことにしましょう。
ちなみに「ダイ」と音読みするのは、ダイサギ、ダイシャクシギ、ダイゼンくらい。ダイゼンは「大膳鷸」で宮中料理と関係があるのだとか。
ソバやラーメンでも、オオ盛りは訓読み、チュウ盛りは音読み、コ盛りは訓読みですから、こういう「揺れ」は日本語の面白さということにしておきましょう。
ところで、ダイサギには亜種が存在します(亜種ではなく種として扱うことになったという話も聞きますが、よくわかりません)。ここから話が厄介になります(というか、勝手に厄介にしようとしています)。
日本で見られる亜種はそれぞれ「オオダイサギ」、「チュウダイサギ」と呼ばれていました。
ちなみに図鑑を参考にしてかいてみるとオオダイサギは左のようになるみたいです。面倒くさがって大きさを同じにしてしまいましたが、オオダイサギのほうが大きいそうです(いずれにしても、私は見分けようと思ったことはありません)。
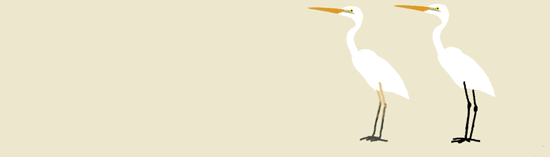
アカハラにはオオアカハラ、カワラヒワにはオオカラワヒワという亜種がいます(私には見分けられません)。トラツグミにも亜種オオトラツグミが奄美大島にいるそうです(とても少ないらしいです)。
また、メボソムシクイには亜種コメボソムシクイがいます。亜種カワラヒワをコカワラヒワと呼ぶことがあります。トラツグミはコトラツグミという亜種が西表島にいるそうです(とても少ないらしいです)。
なので、ダイサギの亜種を書き分ける場合も「オオダイサギ」とか「コダイサギ」にすればいいわけです。
でも、小さい方に「コ」ではなく「チュウ」をつけているのは、「コダイサギ」だと「小大鷺」と、あまりにも矛盾した(亜)種名になってしまうからでしょう。
※でも「新古車」という言葉だって大いに矛盾しているではないかっ!と憤りを感じる方もいると思いますが、それは当サイトの守備範囲外です。

ところで「中古車」の「中」ってなんでしょうね?すこし古いってこと?ならば、すごく古い車は…オールドカーとかクラシックカーになるのかな。日本語だと「古車」??。
ここまでは分かります(話は、コダイサギだと矛盾するので、チュウダイサギには納得できるというところまできました)。
でも問題は(というか、勝手に問題にしているのですが)、漢字で書けば「大大鷺」となるこの亜種(種)を、「オオ(訓)ダイ(音)サギ」と「大」の漢字を音訓混ぜて読ませたことです。漢字で書かれたら、絶対オオダイサギとは読めません(漢字では書かないと思いますけど)。
「オオダイサギ」と音訓ねじって読むより、「オオオオサギ」にしちゃうか「ダイダイサギ」と読むのが自然。ただ、オオオオサギだと和名が変わってしまうので、ダイダイサギしかありません。
※ちなみに「オオオオ」の読み方についての研究はこちらをご覧下さい。
検索してみると、「ダイダイサギ」という言い方も一般的に使われているようです。こっちの方が自然で読みやすいのですから、当然です。
ただ、アオサギとかムラサキサギという種類があることを考えると(アマサギやクロサギもそうですが)、「ダイダイサギ」と読む場合の最大の問題点は、下のようなダイサギを想像しかねないことです(というか、この記事はこのイラストをかいてみたくて、無理矢理ここまで引っ張ってきました。オチは見えてましたよね。お付き合いいただき、ありがとうございました)。

無理せず、亜種「ダイサギ」と亜種「チュウダイサギ」にしておけばよかったのに…と思ったのはもちろん私だけではないようで、現在は、「ダイサギ」「チュウダイサギ」が正式な亜種名になっているとのことです。安心しました。
2010年1月記
参考文献:「図説 鳥名の由来辞典」菅原浩・柿澤亮三編著・柏書房・2005年/「コンサイス鳥名事典」吉井正監修・三省堂・1989年/「山渓ハンディ図鑑日本の野鳥」叶内拓哉・安部直哉・上田秀雄著・山と渓谷社・1998年
