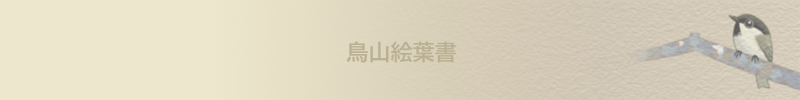野外手帳
-2024年11月
オオバン落鳥
2024年12月1日記
近くに池や川など水辺はなく、胸元に血が滲んだ外傷があるので、別の場所で何者かに捕らえられ、その後何らかの理由でここに置き去りにされたのだと思われます。これは偏見かもしれませんが、外猫をその犯人として疑ってしまいます。

2024年12月2日追記
この話をSNS(Mastodon)に上げたところ、「鳥インフルエンザで死んだ個体を何者かが運んだ可能性がある」という指摘をいただきました。確かにそちらの方があり得る話かもしれません。安易に外猫と結びつけるべきではなかったです。
ルリビタキとアオジが山から降りてきた
2024年11月30日記
夕方の里山山麓です。写真はありませんが、歩き始めてすぐ、ルリビタキを見ることができました。今シーズン、平地ではこれが初認です。これでこの日の目的を達成した感じがしました。

すぐ近くの藪にはアオジがいました。これも今シーズンの平地での初認となりました。

山道に入る前の柿の木にメジロが来ていました。

山道に入ってからはヒガラやシジュウカラなど。

今年の秋は暑さのせいか、冷え込みが弱かったせいか、紅葉・黄葉はあまり鮮やかではありませんでしたが、山の中に入るとそこそこ楽しめました。

時間がなかったのでほんの少し登ったところで引き返し。

木々の間から白くなった里山が見えていました。
ベニマシコとシロハラ初認
2024年11月30日記

11月中旬は咳に悩まされていて、畦道を歩いたのは半月ぶりになりました。

ようやく里山が白くなりました。夕方になっても溶けないままで、やっと冬が近づいてきた実感が湧きました。

私が歩かないでいる間にリンゴの収穫は終わっていました。このリンゴ畑の先の草地でベニマシコの声を聞きました。今季初認です。

柿を食べるヒヨドリ。

私が近づくと地面から電線に上がって様子をうかがうスズメ。

いつもの近所の森へ接続。
ここではシロハラを初認し、ツグミの声も聞きました。

雲に隠れていた太陽が森に赤い光を差し込み始めました。

夕日に照らされたエナガです。

太陽はその上に彩雲を作りながら沈んでいきました。
再びマミチャジナイ
2024年11月24日記
11月上旬、再び畦道を経由していつもの近所の森まで歩きました。

穂先で休むヤマトシジミ。

葉の上に止まるベニシジミ。

草むらに見つけたモンキチョウ。

いつもの近所の森の近くで、マミチャジナイを確認。ここでは飛び去る姿しか撮れませんでした。


少し離れた柿の木に再びマミチャジナイを見つけました。柿は彼らにとって大事な栄養補給源になっているようです。

この画像はかなり無理して暗部を持ち上げています。

もちろんヒヨドリも登場。


メジロも何羽かいました。

里へ現れてしまうクマ対策で、収穫の対象にならない柿の木を伐採する動きがあるようです。こうした柿を頼りにしている鳥への影響はちょっと心配になるところです。

暖かな11月でしたが、群馬との境の山にはうっすら冠雪が見られました。

家に戻る頃には夕空に上弦の月が白く輝いていました。
この日上弦だった月は、これを書いている今は下弦を過ぎました。
仕事がハードモードになったせいか、体調を崩して咳がひどくなり、しばらく外歩きは控えざるを得なくなりました。夜眠れないほどの咳になってしまい、吸入薬を処方してもらって1週間、やっと咳がおさまりまった今日この頃です。
クロコノマチョウとマミチャジナイ
2024年11月23日記

11月上旬のいつもの近所の森です。

見慣れない蝶がいました。その場ではわからなくて、家に帰ってから調べたらクロコノマチョウだとわかりました。初めて見ました。
クロコノマチョウは暖地性の蝶で、本州では東京周辺から西の太平洋岸で見られると図鑑の分布図からは読み取れます。
本来長野で見ることがないはずの蝶なので、これも温暖化の影響なのでしょう。一昔前は見られなかったツマグロヒョウモンが、今は当たり前のように見られるようになったのと同じ経過を、これからこの蝶もたどるのかもしれないです。
最初は暗くてぶれた写真しか撮れませんでしたが、低くなってきた太陽の光が森の中に差し込んできて、ちょうどこの蝶を照らしてくれました。まさに「黒木間蝶」の名にふさわしい状況でした。

西日は蝶だけでなく、木々の葉をも照らしていました。

太陽が沈んだあと、先日聞いたマミチャジナイだと思われる地鳴きが聞こえてきました。

丹念に探していくと、やっと姿を見つけることができました。もう暗くなってきていたのでぶれ気味でしたが、証拠写真も撮れました。

細い月が見えてきたので、西の空が開けている場所まで行ってみました。

ミノウスバ 一時の輝き
2024年11月22日記

庭のマサキにミノウスバが発生していました。暖かい秋のせいか例年より遅めです。

人によって意見は分かれるかもしれませんが、私にとっては美しいと感じる蛾の一つです。成虫には口がなく、この姿は繁殖のためだけの形態だと言えます。
印象的な体色でもあるので、一時の輝きなんていうタイトルの記事にしてしまいましたが、完全にこれは私の勝手なセンチメンタルですね。

マサキを電動ヘッジトリマーで剪定していた時、たくさんの幼虫が糸を吐いてぶら下がり、「避難」していたのを見たのは4月のこと。
調べてみると3月に孵化して幼虫になったミノウスバは5月には蛹化し、晩秋まで蛹のまま過ごすとのこと。彼らの生活史からすると、成虫として過ごすのはほんのひと時なのですね。

卵のようなものが写っていました。ミノウスバは卵で越冬するわけです。

同じマサキにはウラギンシジミの姿もありました。

ウラギンシジミは成虫越冬です。

キタテハ。これも成虫越冬。頑張れよ。

ヤマトシジミ。幼虫越冬の蝶です。家の庭にはカタバミがたくさんあるので、探せば卵や幼虫が見つかるのでしょうが、見たことがありません。
近所の森から周辺へ探蛾探蝶
2024年11月21日記
11月上旬、いつもの近所の森です。

やっと色づきが進んできました。

ムラサキシキブ。

シジュウカラ。鳥は他にエナガなど。そして大型ツグミの地鳴きを聞きました。これまでの観察例からしてマミチャジナイっぽいです。でも姿を捉えることはできませんでした。
森から出て、近くの農耕地から住宅地を歩いてみます。

暖かい日でホトケノザにホウジャクの仲間が飛んできていました。家で見るホシホウジャクとは違う種類だいうことはわかりましたが、写真に撮らないと同定はもちろん無理でした。

ヒメクロホウジャクでよいと思います。

ホトケノザにはチャバネセセリも来ていました。

ウラナミシジミは一頭だけ。かなり傷んでいて、彼らのシーズンは終了と言ってよさそうです。ここまでよく頑張りました。

ヤマトシジミはまだ新鮮な個体が見られます。この時期でもまだ発生しているということでしょう。普通種ですけど美しいですね。

これらの鱗翅類が見られた場所ではテントウムシの幼虫がいました。今年は暖かいからいいようなものの、これで越冬に間に合うのでしょうか。


それからここにはショウリョウバッタやカマキリもいました。何カマキリかは未同定です。

少し離れた場所でキタキチョウ。この時期は多く感じます。

人家の花にクロアゲハ。

図鑑の分布図を見ると長野県にはあまりいないことになっているようです。でも、車の中からときどき黒いアゲハを見ることがこれまでにも何度もあって、それはおそらく本種かジャコウアゲハです。ジャコウアゲハはじっくり見たことがありません。
モズとトンボの秋の畦道
2024年11月20日記
異常なほどにまで暖かだったこの11月でしたが、今日11月20日はついに氷点下を記録しました。もう下旬ではありますが、ここから11月の記録更新になります。

11月初旬の畦道歩き、出発は午前10時半、気温は15℃でした。

このリンゴ畑周辺ではモズの動きが活発でした。

追いかけ合いを観察。

もうあまり高鳴いてはいないものの、縄張り争いは継続中のようです。

柿の木にはヒヨドリ。早くも実をついばんでいました。もう少し寒くなるまで取っておいたほうがいいと思います。

先日住宅街で声を聞いたジョウビタキをついに視認できました。

一度は姿を見せなくなっていたトンボがたくさん連結して飛んでいました。

雨上がりの休耕田は湿地みたいな感じになっていて、そこに盛んに産卵していました。でもここはもう水田ではないのだから、夏になっても水が入ることはないのだよ。ヤゴが育つことができないこんな場所ばかり増えていくのですから、トンボも減るわけです。

ほとんどはアキアカネだったと思われますが、ミヤマアカネもいました。

いっぽうこちらは金属製の橋の欄干に止まっているアキアカネ。この姿はすでに大事な仕事を終え、あとは余生を過ごすだけということなんでしょうか。