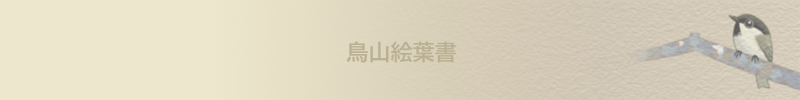野外手帳
-2022年7月
蕎麦畑とヒグラシ
2023年8月27日記

これで7月の記録アップはおしまいです。見頃と聞いてソバの花を見に行ってきました。

クジャクチョウがいました。裏だけだとなんだかわかりませんね。
またここではヒグラシの声を聞きました。この日はヒグラシの初鳴となりました。ニイニイゼミは7月初旬、アブラゼミは7月中旬、ミンミンゼミとヒグラシは7月の下旬が初鳴ということになりました。
サンコウチョウとヘリグロチャバネセセリ
2023年8月26日記
今季サンコウチョウが渡来していることがわかっているので、当然それを期待して歩きはじめます。自宅からそれほど遠くないところでサンコウチョウの観察機会が得られるというのはとても幸せなことだと思います。

そして写真は撮れなかったのですが、しっかりとサンコウチョウを見ることができたことを最初に報告しておきます。
ここは個人的セセリ観察ポイントの3ヶ所目でもありまして、セセリにも期待です。というわけで、ここで撮影したセセリです。

まずこの写真↑から。翅裏の翅脈は太く黒いことがわかります。

翅表です↑。前の記事のスジグロに比べて、前翅外縁の黒い帯が幅広いこと、翅の縁が白っぽく見えることからヘリグロチャバネセセリとしていいのではと思います。

中室外側の黒斑が発達していることもわかります。比較としてスジグロチャバネセセリの中室外側の黒斑画像を↓に載せておきます。

これ↑はスジグロチャバネセセリです。こうして比べてみると、縁の黒い帯の太さの違いがよくわかります。ヘリグロはスジグロよりかなり帯が幅広く、「縁黒」と名付けられたわけがわかるように思います。

ダイミョウセセリ。

ヒメウラナミジャノメ。マタタビ吸蜜中。

コミスジ。

ツバメシジミ。

珍しく翅表が撮れました。

その名の通りのルリシジミ。

産卵行動。

スジグロシロチョウの仲間。

バラシロエダシャクと考えてみました。

かっこいいカメムシ。セアカツノカメムシでいいと思います。

なにかのつぼみ。クサギでしょうか。

オカノトラノオ。

結実マムシグサ。

ニホンアマガエルがたくさんいました。
鳥はサンコウチョウ以外にクロツグミ、ウグイス、センダイムシクイ、メジロ、ヒヨドリ、サンショウクイ、林道を先導してくれたキセキレイ、キバシリ、アオゲラ、コゲラ、キジバト、カケス、ノスリ、ヤマガラ、シジュウカラ、ホオジロを確認です。
鳥も虫も充実していた里山山麓林道歩きでした。
スジグロチャバネセセリなど
2023年8月26日記

某所の森歩きです。前にアカセセリを見た場所以外に、少なめのセセリを見ることができる場所を2つ知っていますというか、見つけてあります。今回はその一つです。サラシナショウマがまだつぼみ、シンミズヒキやヌスビトハギが咲き始めていた7月末の記録です。
さてセセリですが、写真は3枚だけ。

スジグロチャバネセセリ。準絶滅危惧種です。翅の縁は淡い朱色に見えます。

翅の縁が、スジグロチャバネセセリに比べて白っぽく見えるとヘリグロチャバネセセリです。この画像だと翅の縁はかなり白く見えますが、これもスジグロチャバネセセリでいいと思います。

同じ個体を別角度から。この写真でも翅の縁は白く見えますが、淡い朱色に見えないこともありません。
前翅外縁の黒い帯が比較的細い点はスジグロチャバネセセリのオスの特徴と合います。

また前翅中室に黒い性標があること(↑画像)や

中室の外の黒斑が発達していないこともスジグロチャバネセセリのオスの特徴と合います(↑画像)。
というわけでこれはスジグロチャバネセセリと考えていいと思います。
この蝶が見られるということだけでも本当にここは貴重な場所です。

幸先よいスタートを切って、気持ちよく歩いていくとツバメエダシャクの仲間がいました。この蛾も見るだけでテンションが上ります。
前後翅に走るラインはやや茶色を帯びています。この点で、ある程度シロツバメエダシャクかウスキツバメエダシャクではないかと考えることができます。この仲間で重要な識別ポイントは顔の色ですので、なんとかそこは画像で抑えたいところ。そっとアングルを変えて撮影を試みます。

一度飛ばれてしまいましたが、なんとか顔の画像を得ることができました。顔にはオレンジ色が見えます。と、その前に触角がひげ状になっていることに気づきました。この特徴を持っているのはシロツバメエダシャクのオスだけなので、これで同定できたことになります。

アミメリンガ。久しぶりに見ました。とてもいいデザイン。

キベリシロナミシャク。かなりの美麗蛾だと思います。

これはよくわからなかったのですが、ミスジツマキリエダシャクに似ているところがあると思いました。

マダラエダシャクの仲間。この仲間は同定することを諦めています。

イカリモンガ。

スジグロシロチョウの仲間。

ちょっと遠くて不鮮明なのですが、シータテハと考えてみました。

ノリウツギにアカハナカミキリ。

ハバチのイモがいました。体には多少ろう物質が見えます。

歌っていたホオジロ。鳥はほかにアオジ、ウグイス、クロツグミ、イカル、ホトトギス、ヒガラ、アカゲラ、ヒヨドリ、トビを確認しました。

チダケサシ。

林床にはコバノフユイチゴの結実が見られました。

戸隠で見たことがあるハナビラタケをここでも見つけました。ここでは初めてです。
八方尾根の花 3
2023年8月19日記
「2」の続きです。

高山植物らしさをすごく感じるホソバツメクサはナデシコ科。

クモマミミナグサもナデシコ科。
今回、ハコベの仲間はナデシコ科だという知見を得ました。
これまでは科のまとまりごとに紹介してきましたが、ここからはばらばらに紹介です。

ミヤマムラサキ:ムラサキ科

タカネマツムシソウ:マツムシソウ科

トキソウ:ラン科

ミヤマダイモンジソウ:ユキノシタ科

ハクサンタイゲキ:トウダイグサ科
ハクサンシャジン:キキョウ科
イワイチョウ:ミツガシワ科
オトギリソウの仲間:オトギリソウ科

イワカガミ:イワウメ科
ゴゼンタチバナ:ミズキ科
ミヤマウイキョウ:セリ科
オヤマソバ:タデ科
まさに花の八方尾根という山歩きでした。
八方尾根の花 2
2023年8月19日記
「1」の続きです。普段着目していなかった「科」ごとに分けてまとめてみました。
今回の八方行きでよかったのはチングルマをたくさん見ることができたことです。最近は花が咲き終わった群落を目にすることが多かったです。
でこのチングルマはバラ科。草ではなく木であるということです。

丸山ケルン直下にお花畑がありました。

綿毛になっていたものもありました。


ミヤマキンバイもバラ科。キジムシロにそっくりです。

他にもミヤマダイコンソウもバラ科。名前からするとちょっと意外です。

ゲレンデにはとてもたくさん咲いていたシモツケソウ。

斜面を覆い尽くしていたオニシモツケ。

ところどころで見かけたイワシモツケ。
これら、シモツケと名前がついているものはいずれもバラ科でした。ただ、シモツケソウ(オニシモツケも)とシモツケ(イワシモツケはこっち)は名前は似ているものの、バラ科の中では離れた存在であるとのことです。

左はイブキジャコウソウ、右はタテヤマウツボグサ。いずれもシソ科だというのはわかります。

このミヤマコゴメグサも花の形はシソっぽいなと思っていたら全然違いました。ずっとイブキジャコウソウの仲間だと勘違いしていました。こちらはゴマノハグサ科だということです。

シオガマもゴマノハグサ科。左エゾ、右ヨツバです。

花の形が全く違うクガイソウもゴマノハグサ科。

これもゴマノハグサ科のミヤマママコナ。
つづきはこちら。
八方尾根の花 1
2023年8月19日記
八方尾根を登りたくなる理由の一つはやっぱりこの花を見たいからです。

ハッポウタカネセンブリです。

ステキデザインです。こうしてみると、私の中でステキデザインの花と言ったら真っ先に名前が浮かぶアケボノソウとよく似ています。調べてみると、同じリンドウ科とのこと。
ふだんあまり花の「科」には注目していなかったので、今回は科ごとにまとめてみることにしました。
今回の八方尾根で同じリンドウ科に属する花を1つ撮ってきていました。

ミヤマリンドウです。タテヤマリンドウとの違いはいろいろあるようですが、自分がわかりやすいと思ったのはタテヤマリンドウには花の中に斑点があるということです。

八方尾根の固有種といえば、このハッポウウスユキソウも外せません。ウスユキソウの仲間ということはもちろんわかるのですが、何科かを意識したことはありませんでした。調べてキク科ということがわかりました。やや意外。

キク科の花で、わかりやすいのはウサギギク。

ミヤマアズマギク。

クモマニガナ。花弁が11枚だと本種ということですが…。

アザミも言われてみればキク科の雰囲気ありますね(オニアザミ)。

八方池から上には非常にたくさん咲いていたミヤマキンポウゲ。これはキンポウゲ科だとすぐわかります。
ほかのキンポウゲ科の花は…というと、すぐには思いつきません。図鑑で見てみると、サラシナショウマ、レンゲショウマ、リュウキンカ、セツブンソウ、トリカブト、ニリンソウ、キクザキイチゲ、オダマキ、フクジュソウなどがキンポウゲ科でした。普段の山歩きでよく目にする花です。
でも今回はこの花だけが撮ってきたキンポウゲ科でした。

モミジカラマツです。

続いてはユリ科。これはクルマユリです。

八方池までにたくさん咲いていたキンコウカ。これはちょっとユリ科のイメージとは違います。

さらにネギの仲間がユリ科だということにも驚きました。これはシロウマアサツキです。
続きはこちら。
丸山ケルンまで
2023年8月19日記
ほぼ3週間前の山歩きの記録です。有給を取って八方尾根に行ってきました。
電気の力をお金で買ってぐんぐん高度を稼ぎます。毎回ゴンドラやリフトに乗って思うことは、この山(唐松岳のことですが)を麓から歩きで登るとするとかなり深い山であるということです。

平日だったのでそれほど混んではいませんでしたが、学校登山が3組ほどいて、歓声の響く山ではありました。

今回は八方池よりもう少し上まで行くことにしました。

下ノ樺、上ノ樺を抜けていきます。


ここまで来ると平日らしい静かな山になりました。

扇雪渓。

積雪のすごさを物語るタケカンバの寝姿です。

丸山ケルンに到達、今回はここまでです。

まだ時間は早いし、あとは登ってきた道を戻るだけだしと気持ちは楽だったのですが、下山の途中からだんだん膝に痛みが出てきてしまいました。膝の内側の痛みです。
何年もまともに山を歩いていないとこうなってしまうのだなと思い知らされました。前ならもっと早くに出発していたとはいえ、唐松頂上まで日帰りも余裕だったのに。
しばらくは、鳥見や花見よりも歩きを重視して山に行ったほうがいいかもしれないと思いました。

下りではホシガラスの小群を目撃。他には下のゲレンデでホオアカ、扇雪渓でルリビタキ、丸山ケルンでイワツバメを視認。ほかホオジロ、ウソ、メボソムシクイ、ウグイス、、カヤクグリを記録しました。
花については別記事にします。
アカセセリなど
2023年8月18日記
某所でのセセリ探し。

アカセセリのオス。絶滅危惧種です。後翅は赤茶色、小さな淡い斑点があります。

この画像では斑点はあまりはっきりしません。コキマダラセセリは斑点がもっと大きいようです。

前翅表側です。外縁の黒い帯ははっきりと太くて、細いコキマダラセセリとは異なります。

性標の中に白い細い線があるのも、アカセセリならではの特徴ということです(上画像)。
つづいてはメスの画像です。

翅裏はオスに比べて緑がかって見えます。淡い斑紋が小さいという特徴はオスと同じです。

メスの翅の表側です。

これはコキマダセセリのオスと考えました。ヒメキママダラセセリは翅脈が黒いということです。似たような赤茶色系のセセリで翅脈が黒いものは他にもスジグロチャバネセセリとヘリグロチャバネセセリがいます。

翅脈がはっきり太く黒いことと翅の縁がかなり白く見えることから、ヘリグロチャバネセセリと考えます。
セセリはここまで。これだけセセリが見られる場所は、個人的にはなかなか貴重です。特にアカセセリの分布はかなり限られているということなので。

すれていて私には難しいです。ヒメシジミでしょうか。

丸で囲った黒い点が、ヒメシジミではほぼ円形、アサマシジミやミヤマシジミでは楕円形という違いがあるそうですが、例外もあるらしくちょっとはっきりしません。ヒメシジミは準絶滅危惧種です。

ウラギンヒョウモン。

モンキチョウです。
初めてのスミナガシ
2023年8月18日記
ごみ出しに行ったときに、隣の家の壁に張り付いているのを見つけました。前から見たいと思っていた蝶との初めての出会いがこんな形になるとは思ってもいませんでした。

ごみを出した後、家に戻ってカメラを持ち出して撮った1枚です。
夏の花咲く戸隠森林植物園
2023年8月18日記
前回から1週間後の戸隠森林植物園です。

休日ですが、花も鳥も観察にはあまり適さない季節のせいか、駐車場はがらがらでした。

まず、エゾアジサイはますます美しく。

それから、シキンカラマツは見頃を迎えていました。

そしてこの時期に気になる花の3つ目、タマガワホトトギスです。

花の数は少なめでしたが、楽しむことができました。

ミズバショウばかりが注目されがちな戸隠ですが、季節をかえて歩くことでいろいろな花に出会うことができます。

前回に比べて増えてきたと感じる花の一つ、コバギボウシ。

そしてこれが謎なんですが、ランの仲間であることは確か。でもしっかり花の形を撮ってこなかったのでよくわかりません。
ツレサギソウ属っぽく見えて、その中でもオオヤマサギソウに近いように見えますが、手持ちの図鑑にはオオヤマサギソウは載っていません。webで検索してもこれ!というページに行き当たることができませんでした。

咲き終わって身をつけていたのはサンカヨウ。その実もすでに落ちてしまっていました。

クリンソウ。
盛夏をイメージする花々。

ヌスビトハギ。

キツリフネ。まだ数は少ないです。

ノブキ。これからの小径脇に咲く花の主役です。
これから咲こうとする花々。

まずは植栽ですがレンゲショウマ。

マルバダケブキ。

その他の花々(↑↓)。


オオウバユリにはアカアシカスミカメがくっついていました。

ノリウツギにくっついていたのはハバチと思われるイモムシ。オオコシアカハバチでしょうか。

アカハネムシの仲間。

ヒメスジコガネあたりでしょうか。

初めて見るカミキリ。背中に黒いコブみたいなものが2つくっついているのがわかります。コブヤハズカミキリと考えてみました。

鱗翅はこのくらい。少なかったです。

前回と同様、ハチクマが鳴きながら飛んでいるのを観察できました。鳥はほかに、アオジ、ノジコ、、ウグイス、キバシリ、コガラ、アカハラ、クロツグミ、キビタキ、ホトトギス、カイツブリ、カルガモを記録しました。

今年もハナビラタケがぐんぐん育っています。
梅雨明けの日
2023年8月15日記
7月下旬の某所、梅雨明けの日でした。

標高は1000mを超えているので、正午でも気温は25℃とまあまあさわやかでした。

花はこんな感じ、ツリフネソウは一輪だけ。これが辺り一面に咲くようになると、もうすぐ秋ということになります。

シキンカラマツも咲いていました。写真にするのは難しい花ですが、このカットはわりと気に入っています。

キヒゲアシブトハナアブ。自然度の高いところにしかいないそうです。ここはあんまりそんな感じはしないんですけど、環境的にはいいということなのですね。このアブの名前は覚えられません。毎回調べることになります。

コヒョウモンがいました。ヒョウモンチョウに比べれば「普通」に見られると言ってもいい種類ですが、図鑑の分布図を見ると本州での分布は限られていることがよくわかります。

鳥は少なかったです。視認はコゲラ、アカゲラ、ゴジュウカラ、キジバト、モズ、オオヨシキリ、アオジ。そしてこの鳥。

ちょっと迷ったんですが、コサメビタキでいいですよね。

虫も少なかったです。右下の蛾はよく見るタイプですが、くわしくはわかりません。Archips属ミダレカクモンハマキかオオアトハマキかなんかだと思います。
鱗翅類に期待して歩いたので少々物足りませんでした。でも梅雨明けのさわやかな天気と空気の中を、生き物を探しながら歩くことは、やはり楽しいことです。
戸隠7月中旬の鳥と虫
2023年8月15日記
戸隠7月中旬の花のつづき、鳥と虫です。

印象的だったのはハチクマが鳴きながら飛んでいたこと。梢の隙間から飛んでいる姿を見ることができました。

池にはカイツブリの幼鳥がいました。

ずっとここで過ごすわけではないと思います。カイツブリを飛ぶところを見たことがありません。おそらく飛ぶことは得意ではない鳥だと思います。いつ、どうやって、どこへ移動していくのでしょうか。そして行き先(池や湖など)を見つけてそこに降り立つことだって、かなり難しいことだと思います。

トンボは難しいです。左下は一見シオカラですがシオヤトンボだとわかるようになりました。

ヤゴの抜け殻も発見。

スジグロシロチョウの仲間。メタカラコウで吸蜜中でした。

今年も戸隠で会えたコヒョウモン。この画像だと前翅の丸みがよくわかります。これがよくにたヒョウモンチョウとの違いの一つと言われています。

ミドリヒョウモンのペア。左の緑味が強いのがメス、右の前翅に太い4本の性標が目立つのがオスです。

ハバチの幼虫だと思われます。ロウ物質をまとっているのでクルミマルハバチかもしれません。
戸隠7月中旬の花
2023年8月15日記

7月中旬の戸隠森林植物園です。鳥的には葉が茂っているし囀りのシーズンでもないしあまり期待できないのですが、毎週のように変わっていく咲く花との出会いが魅力的です。

魅力的な花の一つがこのエゾアジサイ。青がすてきすぎます。

同じようなカットばかりですが、魅力的なので何枚も撮ってしまいます。

それからシキンカラマツ。この花は撮るのが難しくてどう撮っても絵にならないです。

どれもしっくりきませんが、このあたりが自分の限界です。

そしてタマガワホトトギスです。今年はちょっと花期を外してしまった感じでした。

最近名前がすらっと出てくるようになったケナツノタムラソウ。

メタカラコウ、バイケイソウ、ヤマホタルブクロ、よく見てこなかったですけどたぶんコオニユリ。

ズダヤクシュは結実。前回ここに来たのは6月でそのときズダヤクシュはちょうど盛りでした。

早くも秋の気配、ミゾソバが一部で咲き始めていました。
鳥と虫は別記事で。
庭にて
2023年8月15日記

ツマグロヒョウモン。翅裏の美しさよ。

ムシヒキ系。
蛾は難しいね
2023年8月15日記
「梅雨明けのような日の花と蝶」の続きです。蛾と鳥いきます。

キンモンガ。ゴイシシジミもキンモンガもここでは過去にはもっと多かったように思います。

シロモンクロエダシャクでいいと思います。

そしてこれもたぶん同種。蛾の同定に取り組み始めたとき、とても苦しんだ種類の一つです。この画像も図鑑に載っている典型的な斑紋とは違います。

ベニシタヒトリ。この蛾は飛んでいるときにはものすごく後翅のオレンジが目立ちます。飛んでいく先を目で追って、とまったところを見つけようと思うのですが、とまるとこのように一気に地味な姿になって、発見が困難になります。

ウスオビヒメエダシャク。これは見たとき名前は出てこないものの、あああれね!というところまで来た蛾の一つです。
こうして葉の表にとまってくれる蛾だけが私の守備範囲です。蛾は飛び立っても葉の裏側に潜り込む種類が圧倒的に多くて、本当はそういうのもていねいに見ていけばいいんでしょうけど、そこまでは長野方言で言う「ずく」が出ません。

でもたまーにこうして葉の裏に止まっている姿を見つけられることもあります。これもウスオビヒメエダシャクですね。
あとライトトラップを仕掛ければ見ることができる蛾の種類はぐっと増えるのでしょうけど、まあそこまですることもないかなと。

よくわからない蛾。

甲虫も少し。ヨツスジハナカミキリ。

アオジョウカイ。顔が花粉?で汚れています。

アップの図。
トンボも少し。

アキアカネ。

カワトンボ系。
さて鳥です。確認できたのは、ホトトギス、キジバト、、アオジ、ノジコ、シジュウカラ、ヒガラ、コゲラ、アオゲラ、ウグイス、ミソサザイ、ノスリ、トビでした。撮影できたのはシジュウカラだけです。

嘴に黄色みが残っているので幼鳥ですかね。かわいいやね。

梅雨明けのような日の花と蝶
2023年8月14日記

7月中旬の特に場所を秘す某所です。まるで梅雨が開けたかのような天気でした。この日、東北ではかなりの梅雨末期の豪雨で大きな被害が出ていました。
いつも思うのですが、梅雨に入ったとか開けたとかいちいち宣言する意味ってなんなのでしょう。秋雨前線が停滞したときにはそんなアナウンスはないわけですし。

バイケイソウが咲き始めていました。この花は咲き始めの頃が一番きれいだと思います。

メタカラコウ。オタカラコウとの見分けがいい加減でした。

ウツボグサ。デジタルカメラでは正しい色が出ない花の一つです。ニコンだけ?

オカトラノオ。昔はオカ「ノ」トラノオと勘違いしていて、この野外手帳でも古いものにはその誤記が残っているかもしれません。この花はこうして少し引いてもいいですし、

こうしてアップで撮ってもいいです。
ここからは少し晩夏から秋っぽいイメージの花。

まずはヌスビトハギ。

キツリフネ。

ケナツノタムラソウ。まあこの花は秋というよりその名の通り夏の花ですが、アキノタムラソウにイメージが引っ張られてます。

この花で吸蜜していたスジグロシロチョウ(またはヤマト)。

手乗りサカハチチョウ。

クロヒカゲ。

ミドリヒョウモンは今季初めてでした。

ダイミョウセセリ。名前の由来が気になる和名です。
大名の裃に似ているという説と大名行列のときに伏している姿に似ているという説があるようですが、いずれにしてもこの翅を開いて止まるところから来ている印象です。ほかのセセリは翅を閉じたり半開きにしていることが多いですから。
ちなみに学名も“Daimio” tethysなんですね。

ゴイシシジミもいました。でも前はもっとたくさんいたように思います。今季は少ない印象です。

駐車スペースの砂利のところにいたスジボソヤマキチョウ。
少し長くなったので、続きは別記事にします。
7月最後の畦道
2023年8月14日記
7月の2つ目も畦道散歩です。前回(↓トンボがいる田んぼ)から1週間後です。気温は28℃でしたがとても蒸し暑く感じた日でした。

モズがあちこちでギチギチ鳴いていました。もちとん高鳴きとは違うのですが、何をもって高鳴きとするのかは実はよくわかっていません。いろいろ調べてもよくわかりませんでした。なので高鳴きの初認の記録は今はやめています。

ヒメジョオンで見かけた蛾。後で名前を調べようという軽い気持ちで撮ってしまったのでピンあまです。で、調べてみるとキマダラコヤガという蛾らしい。そして数を減らしている蛾だということでした。もっとしっかり撮っておけばよかったと後悔しています。

晩夏から秋のイメージがあるウラナミシジミを初認しました。

その他のムシムシ。ツバメシジミ、いつも交尾している印象のマメコガネ、たぶんハゴロモの幼虫、ショウジョウトンボです。トンボを撮ったのは例の(↓の)田んぼです。

ニホンカナヘビ。

上陸を始めたニホンアマガエル。
両種とも和名に「ニホン」が含まれます。和名ではニホンがほとんどで、ニッポンとなる例はとても少ないと思います。知っている範囲ではニッポンマイマイくらい。なぜなんでしょう。

花ではヤイトバナが出始め。ヤブカンゾウはかなり盛りになってきて、キスゲフクレアブラムシが付き始めていました。サクラタデ、ガガイモのつぼみ。
これを書いているのはこの日からちょうど1ヶ月後ですが、実はこの日以来畦道を歩いていません。連日のように35℃前後まで気温が上がるなどこの夏は暑すぎて、ちょっと歩く気になれなかったり気温が低いところに逃げてしまったりでした。
1週間後でも花の様子は違いがありましたので、1ヶ月が過ぎた今はきっとかなり違いがあると思います。
今はどんな花が咲いていて、どんな虫たちが見られるのだろうかと少し気にはなっています。でもやっぱり暑すぎです。
トンボがいる田んぼ
2023年8月14日記
お盆なのでどんどん記録をアップしていきます。ここからやっと7月の記録です。

いつもの畦道、まずはぼさぼさのヒヨドリとスズメのツーショットからスタートです。

ヤブカンゾウが咲き始めた頃でした。ヒルガオ、ヤブランも目立つようになりました。

モンキチョウ。AF性能に助けられてやっと撮れた1枚。

ツバメシジミ。ここではあまり多くありません。シロツメクサ、カラスノエンドウなど食草はたくさんあるのに。

ホシミスジ。前翅の一番上の白い横線がシュッとしているのがミスジチョウ、乱れた感じになっているのがオオミスジ、2つに分かれているのがコミスジ、そしていくつにも分かれているのがホシミスジ。

この田んぼはちょっと特別で、トンボがここにだけたくさんいるのです。なかなか撮影は難しいのですが、今回撮れたのはこれ。

ハラビロトンボのオス。

ハラビロトンボのメス。

ショウジョウトンボのオス。
止まってくれないと撮れない、わからないので、ほかの種類もいたかもしれません。この田んぼをすぎるとトンボはほとんど出現しません。近くに木があるのがいいのか、土手の草刈りの具合がいいのか、それとも農薬の使い方の問題なのか。

前回メスのコムクドリを見た電線に、今回はオスがいました。

スズメに始まったこの日の散歩は、終わりもスズメでした。