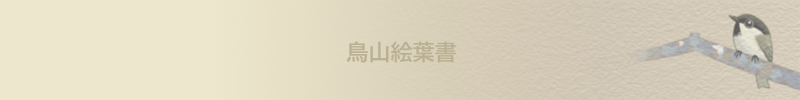野外手帳
-2023年6月
変わっていく畦道
2023年8月13日記

お盆に入りまして更新強化中です。ようやくこれで6月最後の記録のアップです。夕方の畦道です。

この頃の稲はまだこんなだったんだなと、写真を見て改めて季節による風景の違いに気付かされます。
いつも通っている場所で工事が始まっていました。こうしてだんだん馴染みの畦道も変わっていってしまうのだなと思います。
家のすぐ近くにあった畦道は随分前に失われてしまって、そのときはちょっと感傷的になってしまいました。その分、今はこちらの畦道を歩いているのですが、同じようなことが起こっていくのかもしれません。

一方、歩く度に発見もあるわけでして、こんなところにミズキが咲いているんだという新たな知見を今回は得ました。

電線には夕日に照らされたコムクドリ。

まだ幼いスズメと成鳥のスズメ。

アンテナに止まるノスリと屋根に止まるハシボソガラス。

色温度が低くてより鮮やかに見えたベニシジミ。

マメコガネ。この食痕はすべて彼のものでしょうか?

最初に畦道が変わっていくと書きました。工事による変化以外にもいろいろあって、例えば水田は草原になってしまったところが年々増えています。農業の担い手が高齢化したり、後継者がいなかったりが要因だと思います。同じ理由だと思うのですが、リンゴの畑もどんどん少なくなってきています。伐採されて放置されている場所をあちこちで見かけます。
さびしく感じますけれど、ただ単に畦道を歩いているものとしてはどうすることもできません。

水色と黄色の謎イモ
2023年8月13日記
お盆に突入。まだここでは6月の話を続けます。早く記録をアップしなくてはであります。今回のアップ分は6月下旬の特に場所を秘す某所の森歩きです。特別珍しいものがいるわけではないのですが、駐車スペースがとても狭いため、あまり人には知られたくありません。大概は自分ひとりの森歩きになります。

画像はニワトコの実。小学生の頃急性腎炎を患ったことがありまして、ニワトコが効くと聞いた母が探してきて煎じて飲ませてくれた遠い記憶があります。それは実だったのは葉だったのか何だったのか、今となってはわかりません。

そしてこれはマタタビの葉。猫を飼っていたら持って帰って試してみたくなるところです。

林床にはあちこちにコバノフユイチゴが花を咲かせていました。

そしてジンヨウイチヤクソウがようやく開花しました。

小さな小さな花ですがなかなかの存在感です。この日のうれしい収穫でした。

フタリシズカです。花序が2本あるものだと思いこんでいましたが調べてみると1本のことも3本以上のこともあるみたいです。ここのは全て1本花序でした。

イボタノキの花(だと思います)は虫たちに大人気でした。

これはコチャバネセセリ。たくさんいました。

コトラガ。トラガは前翅の白い斑紋が外縁部にもあります。

コアオハナムグリ。もっふもふです。

ササにはゴイシシジミがいました。

これは産卵シーン。この蝶の幼虫は日本産の蝶の中で唯一の完全な肉食性で(ゴマシジミなどはアリの巣の中に入ったら肉食に変身するがそれまでは植物食)、ササにつくアブラムシを食べるとのこと。
と、ここまでは事前に知っていたことですが、この産卵行動を撮ったあとに調べてみると、アブラムシの集団の中に卵を産むということなのです。
写真をよく見るとアブラムシが写っているようないないような。その場でしっかり見てくればよかったです。

オオナミシャク。日本固有種だそうです。葉の表に止まってくれていたので見つけることができました。

非常に分かりにく画像になってしまいました。サカハチクロナミシャクでいいと思います。

蛾を捕食したムシヒキアブ系。よく蛾や蝶の翅だけが落ちていることがあります。こうした営みの結果でしょうか。

カワトンボの仲間。

こちらもですが、縁紋が白。種類が違うのか変異なのかそれさえわかりません。

トンボは同定が難しいのであまり撮らないようにしていますが、これはオオイトトンボでいいでしょうか。

ジョウカイボン。この仲間もいろいろ種類があるようですが、普通のジョウカイボンということにしておきます。

アオジョウカイ。ジョウカイボンの名前の由来は諸説あるとのことです。

アカハネムシの仲間。これ以上の深入りは私には無理です。

ついつい撮ってしまうハエトリ。そして家で悩むことになります。デーニッツでいいのかなー。

これはハバチの仲間のようです。絵合わせからはクロハバチが近いです。

そして今回の最大の問題はこれです。黒い頭に水色の体色、お腹は黄色。こんなに特徴がはっきりしているイモムシなので同定は楽勝と思われましたが、迷路にはまってしまいました。webでいろいろ調べてみるとゼンマイハバチの幼虫と似ているように思われます。
というわけで今回は謎だらけになってしまいました。
その他に確認できた虫はエゾハルゼミ、アサギマダラ(今季初認)、鳥はカッコウ、ホトトギス、ウグイス、ヤブサメ、オオルリ、キビタキ、アオジ、ホオジロ、キバシリ、メジロ、コゲラ、アカゲラ、ヒヨドリ、キセキレイ、サンショウクイ、キジバト、コガラ、シジュウカラ、ヒガラです。
クマに会いませんように
2023年8月12日記
「銀一文字」と「顔白」を見た後、少し移動して亜高山帯の森歩きをしました。

最近この周辺では、ツキノワグマの目撃事例が増えたり事故も起こったりしているので、だんだん足が向かない山域になっています。
以前は熊鈴を鳴らして歩くことには少し抵抗がありました。でも今は必ず鳴らすようにしています。別の場所ではありますが、今年はすでに一度クマに会ってしまっていますので。

なのでガサガサ!と藪の中で物音がすると身構えてしまいます。
この日の音の正体はクロジでした。上の画像は「クロジをさがせ!」的なものになってしまいました。保護色として優秀だということでもあります。
その他の鳥は、ヒガラ、コガラ、エナガ、コゲラ、コルリ、ルリビタキ、ウグイス、センダイムシクイ、ヤブサメ、ミソサザイでした。

花は上のツマトリソウ、下のゴゼンタチバナ、マイヅルソウ、ギンリョウソウなど。



こうして草花をしゃがみこんで撮影した後再び歩き始めるときには、しばらく鈴を鳴らしていないことになるので、よけいに気をつけなければいけないと思います。
この日もそんな心がけをしながら歩いていたのですが、なんと数十人の団体とすれ違うことになり、それからはクマの心配をあまりしないで歩くことができました。人が多い山は苦手ではありましたが、これからはあまり静かな場所は避けたほうがいいのかなと思います。
銀一文字と顔白
2023年8月12日記

8月に入り、毎日毎日酷暑が続きます。今年の夏は特別に暑い感じがします。雨もほとんど降らないですし、生き物たちにとってもかなり厳しいのではと思います。
6月の記録を書くためにエアコンの効いた部屋でその時の写真を選んでいました。更新がまたも遅れてしまいました。6月下旬の高原です。まだレンゲツツジが咲いていた季節です。

この日の目標の一つだったギンイチモンジセセリを、歩きはじめてすぐに見つけることができました。都市近郊でも見られるとのことですが、準絶滅危惧種です。ここはこの蝶を確実に見られるポイントとして、私の中では貴重な場所になっています。

翅の表は一色で特徴がありません。翅裏はそれはそれは美しいデザインです。

他の鱗翅も期待してたのですが、写真に撮れたのはこのツメクサガだけ。そのほか、モンキチョウとタテハの仲間を見ただけで、数的にはかなり寂しい感じでした。

ここはイタドリが多い場所でもあって、当然のようにイタドリハムシもたくさんいます。

花はアカモノ。

コケモモ。

そしてハクサンシャクナゲです。

この時点ではニッコウキスゲはまだほとんど咲いていませんでした。

ガスに見え隠れする森を眺めながら近くの湿原へ足を進めます。

ワタスゲの見頃はちょっと外してしまった感じでした。

モウセンゴケ。木道からはとても撮れません。足元に生えている場所を見つけて撮りました。

ヒメシャクナゲ。寒冷地の湿原ならではの花です。

ヒオウギアヤメ。これも北方の湿原の花です。温暖化が進めばこれらの花は見られなくなってしまうのでしょうか。

ここでは今日のもう一つの目標だったカオジロトンボを見ることができました。山の湿原を代表するトンボです。
木道が大好きのようで、必ずと言っていいほど木道に止まります。葉先とかに止まっている写真を撮りたいと思うのですが無理でした。
このあと、更に亜高山帯の森を歩きましたが、その記録は別記事にすることにします。
幼鳥よ猫だけにはやられるな
2023年7月26日記
6月中旬、いつもの畦道散歩の記録です。自宅発は10時10分、蒸し暑い日でした。気温は26℃。

クワ、リンゴ、クルミの状況はこんなでした。

クワの木にはキボシカミキリがいました。

クルミにはトンボの姿。未同定(ちょっとくやしい)。

一瞬ナナホシのように見えるナミテントウです。

同じヒメジョオンにはカニグモの仲間。

ナヨクサフジにはたくさんのクマバチがいて吸蜜を繰り返していました。

畑の角材にはヨコヅナサシガメ。
歩いている間、ずっと遠く近くにカッコウが鳴いていました。ここ数日は自宅周辺で朝カッコウの声を聞くことが多く、この日聞いた声も同じ個体かもしれません。なわばりは結構広いと思います。

電柱のてっぺんに姿を発見。

フェンスにスズメのまだ若い個体がいました。
まだこの時期は人から逃げるタイミングもスピードも遅くて、見ていてちょっと心配になります。成鳥になれずに命を落としてしまう個体は多いことでしょう。
生態系の中で他の生き物の食べ物になるのは仕方がないというか、それが自然なのですが、このあたりにはずいぶん少なくなったとはいえ、外猫がいます。家の外を出歩いている猫が、多くの野の生き物を殺している現状はもっと知られるべきで、問題にもするべきです。
世の中の外猫に対する認識はあまりにも甘くて、野外でくつろぐ飼い猫をかわいいと感じる方が多すぎると思います。NHKが外猫礼賛番組を流しているもかなり問題で、それに関わる某写真家の罪は大きいと思います。
私は猫そのものは好きですが、野の生き物への影響を考えると、外猫をとてもかわいいとは思えません。猫は終生室内飼育するべき存在だという認識がもっと広まってほしいと強く思います。

あとムクドリ。ほかにはカルガモ(上有空通過)、ツバメ、ヒヨドリ、オナガ、ハシボソガラス、カワラヒワ。キジは声だけ確認です。
最後に鱗翅。

正面顔のベニシジミ。かわいいです。

よく見るけどわからない蛾。キシタホソバと考えます。見た目が似た種類がいくつかあるみたいです(キマエホソバ、ニセキマエホソバなど)。
そのほか鱗翅ではモンキチョウ、モンシロチョウを見ました。
というわけで相変わらず昆虫は同定が難しくてすっきりしませんが、あちこちに幼鳥がわらわらと湧いて出て、楽しい畦道でした。願わくは幼鳥よ、猫にだけはやられるな。
ゴマダラベニコケガ
2023年7月22日記

6月中旬の里山山麓歩きです。林道をたどります。

林道の入口、まだ視界が開けているところで見かけたハシボソガラス3兄弟(?)。

例によって鳥の写真はほとんど撮れません。姿も確認できないことが多く、声だけの記録ばかりになります。キビタキ、オオルリ、クロツグミ、ヤブサメ、ウグイス、シジュウカラ、コガラ、メジロ、ヒヨドリ、サンショウクイ、イカル、カワラヒワ、ホトトギス、ノスリ、トビなど。この日の目標はサンコウチョウで、林道を引き返すところで一声だけ聞くことができました。

上の画像はマタタビ。

左はミツバウツギの実。右はおそらくヒメウツギの花です。

大きなシャクガ。キガシラオオナミシャクでいいと思います。

図鑑でその存在は知っていたものの見たことがなかったゴマダラベニコケガ。この蛾を見ることができただけでも大満足でした。サンコウチョウの確認と合わせて、よい林道歩きとなりました。
※最初スジベニコケガとしてアップしましたが、ゴマダラベニコケガの誤りでした。訂正しました。スジベニコケガは中横線(3本ある黒点が並んだ列の真ん中)が翅の縁で曲がるのに対して、ゴマダラベニコケガはほぼ真っすぐなのが見分けとのことです。
これからも無事に歩けますように
2023年7月17日記
戸隠の白い花のつづきです。


池にはモリアオガエルの卵塊、そしてカルガモの雛の姿。

藪の中に潜んでいたエナガ団子。もちろんすぐに立ち去りました。
鳥の写真はこれだけ。このほかに目視できたのはミソサザイ、キセキレイ、ゴジュウカラくらい。声だけの記録は、カッコウ、ホトトギス、ツツドリ、アオバト、キジバト、サンショウクイ、シジュウカラ、ヒガラ、キビタキ、コサメビタキ、コルリ、クロツグミ、ウグイス、ホオジロ、アオジでした。

カワトンボの仲間。

エゾイトトンボでいいと思います。

今季止まっているところをなかなか撮る機会がなかったウスバシロチョウ。

ヤマキマダラヒカゲ。ヤマでいいと思うんですが。
エゾハルゼミが鳴いていたことは前回書きました。

幸運にも地面近くにいた個体を見ることができました。
実はこのエゾハルゼミを見たすぐ近くで、唸り声とともに黒い獣が前方を横切るのを見てしまいました。距離にして50m。ちょっと心臓がばくばくしました。
鈴をつけると鳥の声はよく聞こえないし、蛾や蝶も逃げがちな印象があるので、本当はあまりつけたくありません。ただ今年はクマの事故のニュースをよく聞きますし、昨年も事故現場にほど違いところを歩いていて、一歩間違えれば危なかったかもという状況もあったので、最近は基本的には鈴を鳴らしています。もっとも鈴でクマが逃げるという保証は全くありませんので、お守りみたいなものです。
人の少ない時季や時間帯は避けたほうがいいかもしれません。これからも無事に戸隠を歩けることを願うしかありません。

最後に見かけたサラサドウダンに、そんなことを話しかけたくなってしまうようなこの日の戸隠でした。

それにしてもなんという素敵デザイン。
戸隠の白い花
2023年7月17日記
6月中旬の戸隠森林植物園です。

曇り時々晴れ、気温18℃のコンディション。エゾハルゼミが鳴いていました。

湿地帯に咲いていたのはバイケイソウです。なかなかみごとな眺めでした。この時季の戸隠の楽しみの一つです。

葉が茂ってしまって探鳥としては今ひとつですが、6月は花のハイシーズン。

林床を埋め尽くすように咲くのはズダヤクシュ。漢字で書くと喘息薬種で、咳止めとして用いられていたらしいです。

小さな地味な花ですが、マクロで撮ると案外華やかです。

白い花が多いです。これはヤブデマリの仲間。

装飾花は蝶や蛾のように見えて、かわいらしいです。

これも白い花と言っていいと思います。ギンリョウソウ。

そしてギョウジャニンニクも白い花です。
その他に見られた花。ここからは白い花とは限りません。

ユキザサ、ベニバナイチヤクソウ、ヤマオダマキ、シロバナノヘビイチゴ。
下の花は、パッと見てランの仲間とはわかりますし、以前にも戸隠で見たことがる!とは思ったのですが、名前が思い出せなかった花。

家に帰って調べてわかりました。コケイランです。漢字で書くと小蕙蘭。蕙とはシランの仲間のことのようです。

エビネにも似ていると思ったら、ササエビネという別名もあるとか。

素人目には蘭には見えないサイハイラン。漢字で書くと采配蘭。

武将の持つ采配に花を見立てているとのことですが、ちょっとぴんときません。

クワガタソウ。漢字で書くと鍬形草で、こりは実の形に由来するとか。

植物の同定をするときに、同じ地域を歩いているブログがあって参考にしているのですが、そこではヤマクワガタとなっていました。ヤマクワガタの花は白かごく淡い淡紫色、クワガタソウははっきりとした淡紫色ということなのですが…。

鏡池まで行って折り返します。

タニウツギでいいでしょうか。

クリンソウ。次回は鳥や虫などです。
デオキノコムシ
2023年7月15日記

6月初旬のいつもの近所の森です。

小道沿いのドクダミが咲き始めです。どこでも見かける花ではありますが、森の中ではひときわ美しく見えるのはなぜでしょう。

イボタノキ。

スイカズラ。前回、あちこちで美しく咲いていたエゴノキの花は終わってしまっていました。

ああこれは知っている!というレベルになってきたトガリエダシャク。でもまだ図鑑が必要です。

クヌギカメムシの仲間とウズラカメムシ。

アカビロウドコガネでいいでしょうか。右はホソヒラタアブだと思います。

今回一番印象に残ったのはこれです。道からはかなり遠かったのでサンヨンで撮影。キノコムシか?と思いましたが、お尻がぴんと突き出ている特徴から調べてみるとデオキノコムシ(出尾茸虫)の仲間らしいです。ヒメクロデオキノコムシという種名がヒットしましたが、体系的に紹介しているサイトには行き当たらず、たぶんそれというところ止まりです。
鳥はシジュウカラ、ヤマガラ、キビタキ、ウグイス、サンショウクイ、ヒヨドリ、イカル、遠くカッコウでした。
例年この時季はメマトイと蚊に悩まされ始めるので、森に入るのを躊躇します。今回は試しに、ハッカスプレーを帽子(キャップ)のつば両面にたっぷりスプレーしてみました。結果、メマトイは寄っては来るものの、帽子のつばに近い眼に近づくことはかなり減って、効果があることがわかりました。
目標はサンコウチョウ
2023年7月15日記
「6月初旬の某所探鳥」は午前の部、こちらは午後の部です。里山山麓の林道歩きにでかけました。目標はサンコウチョウです。

林道入口の電線にニュウナイスズメがいました。ここではたぶん初記録です。幸先がよい歩きはじめです。

初めて見る蛾。グーグル検索して、アトキスジクルマコヤガとわかりました。なかなかに美しい蛾です。こうして止まっているときに、前翅と後翅の模様(ライン)がぴたりと一致するデザインがすごいと思います。そういう模様の蛾は結構多いですが、進化のデザイナーはどういう計算でこういう仕様にしているのだろうと不思議に、また神秘的に思います。展翅した標本写真では、ここはわかりにくい点です。

午前中と同じくなかなかとまってくれないウスバシロチョウ、ここでも同様の傾向でしたが、やっと吸蜜している個体に会えました。

個体数が多かったのはダイミョウセセリです。

こうしてみると、ヒメジョオンは蝶にかなり利用されていて、この花がなかったら蝶の生息的にはどうなのだろうと思ってしまうところがあります。

コミスジ。コミスジとホシミスジ、ミスジチョウ、オオミスジの見分けをさっぱり覚えることができなく、毎回図鑑と画像とを照らし合わせています。

ジョウカイボン。

さてニュウナイスズメで始まったこの林道での探鳥は、その後シジュウカラ、コガラ、ヒガラ、ヤマガラ、エナガ、カワラヒワ、ホオジロ、キビタキ、クロツグミ、ウグイス、ヤブサメ、メジロ、ヒヨドリ、コゲラ、アオゲラ、ホトトギス、トビと観察種を積み重ね、この林道引き返し地点(ゲート)で今日の目当てだったサンコウチョウの声も聞くことができました。さすがに姿を見るところまでは叶いませんでしたが、本日の目標を達成です。
6月初旬の某所探鳥
2023年7月15日記
ここから6月の記録です。あまり人には合わない秘密の場所的某所。もちろん小道はあるので、社会的には秘密でもなんでもありません。

この場所での初夏の見どころといえばなんといってもエゾムラサキ。でも6月の初旬で今年のシーズンはおしまいです。茎はかなり伸びていて花期の最盛期とは印象が違います。

アオジやノジコが観察できるこの場所ですが、両種とも声だけ。姿を見ることができたのはホオジロです。

てっぺんに止まっていてたまたま観察できたアオゲラ。曇天空抜けだったので画像は真っ黒になってしまい、かなり強烈に画像処理してあります。
ほかには、コゲラ、オオアカゲラ、カケス、ノスリ、ウグイス、コガラ、キビタキ、ホトトギスなどを記録しました。

林道に出るとカワトンボの仲間をあちこちで見かけました。ウスバシロチョウも観察、写真はありません。今シーズンはどうもウスバシロチョウがなかなかとまってくれません。

林道の花々、まずはベニバナイチヤクソウ。すごくきれいとか、そういう花ではないんですが、写真には撮りたくなる花です。

ササバギンランなどを見て、1時間があっという間に過ぎていきました。