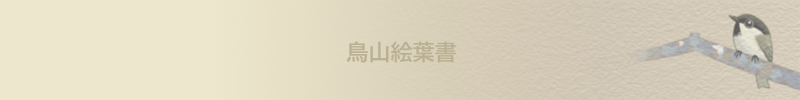野外手帳
-2022年11月
冬鳥がいない
2022年12月11日記
畦道11月8回目。

リンゴの収穫が終わり、カキの実の色だけが目立ちます。

足元に鮮やかな黄色が広がっていました。桑の落葉です。このあたりはおそらくリンゴ畑になる前は一面の桑畑だったのではないかと思います。まだ畦道のあちこちにクワが残っています。この木もその一つ。

すっかり晩秋の風景なのですが、冬鳥がいません。先日はここでもツグミの声を聞きましたが、この日はまったくツグミの気配がありませんでした。カシラダカやシメ、アトリ、ベニマシコなども初認できていません。

たぶんオオタカとこの冬もクロスジフユエダシャク
2022年12月10日記

畦道11月7回目。鳥は少なく写真も特になし。そのままいつもの近所の森に接続しました。

森の入口の道路では、ハシボソガラスがクルミをくわえて飛び去るのを見ました。

紅葉はほぼ終わり、落葉が盛んな森でした。

ヤブランの実はすっかり黒くなっていました。

ムラサキシキブはこの森にはわりと多いです。

畦道では鳥はさっぱりでしたが、ここではまずエナガの群れに囲まれました。

続いてシジュウカラ。写真はありませんがメジロもたくさんいました。しかし畦道同様、ここでも冬鳥の姿がありません。例年ならアトリやシメがそろそろ観察できてもいい時期です。

小鳥を観察していると、猛禽の声が聞こえてきました。声を頼りに探してみると、木の陰にいるのを見つけました。全身を見ることはできませんでした。この森ではオオタカもハイタカも観察したことがあります。お腹のタカ斑模様が細かく感じられるので、オオタカということにしておきます。
このような猛禽が生きていけるということは、この森にはそれを支えられるだけの生き物がいるということです。最近は鳥が少なく感じるのですが、それはここ何年かは午後から歩くことが多いせいかもしれません。

足元にはたくさんのフユシャクが飛び交っていました。なかなか止まってくれないので写真はあきらめかけていましたが、最後の最後に落ち葉に止まっている個体を見つけました。

別個体は翅表側からも撮れました。これで同定可能。クロスジフユエダシャクのようです。もっともこの森ではほかのフユシャクは見たことがないので、最初からそうだとは思っていました。

いつもの近所の森をあとにして自宅に戻ります。

帰り道、ジョウビタキを見ることができました(上写真左下)。でもツグミは3時間歩いたにも関わらず、声さえ聞くことができませんでした。
雨上がりに冬鳥探し
2022年12月4日記
飽きもせずに畦道11月6回目。雨上がり。

数年前は田んぼだった場所。

ここもそう。一面のススキっ原になっていましたが、それを刈ったあと。こういう維持管理は大変ですよね。リンゴの木もどんどん切られているし、当たり前だと思っていた風景がどんどん変わっていきます。
 c
c
まだしずくの残るリンゴの枝先。冬鳥を探しに歩いてみましたが、この日もこの時期としては比較的暖かく、カシラダカやベニマシコなど期待していた冬鳥には会えませんでした。ただ森でしか見ていなかったツグミをこの場所でも確認できて、それが収穫でした。

日が暮れていった
2022年12月1日記
11月畦道5回目。中旬以降は行動範囲が畦道ばかりになっています。

出発は午後3時前、気温は15℃とやはり高めです。

畦道周辺のリンゴ畑は収穫が終わりました。紅葉もほぼ終わったので、これからは色の少ない季節に変わっていきます。

鳥は相変わらず少なく、被写体は蝶くらい。もつれるように飛ぶモンキチョウをあちこちで見かけました。

ヤマトシジミもあちこちで。ウラナミシジミはすっかり姿を消してしまい、季節の進行を感じます。

少し足を延ばしていつもの近所の森に接続しました。一気に鳥が増えて、シジュウカラ、ヤマガラが活発、ジョウビタキやウグイス、メジロ、アカゲラなどを観察。

そしてツグミも見ることができました。まだまだ警戒心が強く梢にとまる枝越しの姿しか見せてはくれません。

天気が崩れるという天気予報通りの雲が出てきました。
冬鳥まだか
2022年12月1日記
11月畦道4回目。

いつも同じ畦道ばっかり歩いているので、逆回りで歩いてはみましたが、休耕田にセイタカアワダチソウが広がるいつもの道でした。あたりまえですね。
セイタカアワダチソウもあんまり大きくならなければ結構爽やかな黄色で、それなりにきれいです。

アブラムシがたくさんいるのか、ナミテントウを見かけました。

冬鳥はジョウビタキだけ。ここでは夏に見られないアオジを観察、一応平地では初認というこちになります。11月にしては暖かい日が続くせいか、冬鳥がさっぱり増えません。
ツグミ初認
2022年11月17日記

11月の畦道3回目。午後2時過ぎから2時間歩きました。気温は21℃、とても暖かい日でした。あちこちでモンキチョウが活発に飛んでいました。でももうやっぱりトンボの姿はありませんでした。

この日も前回に続いて冬鳥探し。でも成果が得られないまま、いつもの近所の森まで来てしまいました。

里の秋はいよいよ終盤で、落葉が目立つようになりました。シロハラあたりがいないだろうか…と思いながら探していたら、「あ、ツグミが鳴いた」。

写真左はこの森で見たヤマガラで、右は遠くで鳴いていたツグミです。このあとすぐこの個体は飛び去ってしまいましたが、このあと森の中ではあっちでもこっちでもツグミが盛んに鳴いていて、もうかなりの数がここには到着していたようでした。というわけで、ジョウビタキに次いで2種類目の冬の小鳥を初認しました。

夕日を受けて金色に輝くユスリカの踊りを見て、この日の歩きはおしまいです。
11月8日皆既月食と天王星食
2022年11月17日記
皆既月食の日、もちろん早めに帰ってきました。ベランダからは東の空が見えないので、最初は別の場所に椅子と保温水筒とスコープを載せた三脚、望遠レンズを載せた三脚を据えて、観望開始です。

月が高く昇ったら場所をベランダに移して観望継続です。今回は皆既の時間が長かったのでたっぷり楽しむことができました。
部分食の開始:18時9分
皆既の開始:19時16分
食の最大:19時59分
皆既の終了:20時42分
部分食の終了:21時49分
これまでの月食はスコープにデジカメを接続し、いわゆるデジスコで撮っていました。今回はスコープは眼視専用にして、撮影は一眼レフに任せました。これが正解で、やっぱりスコープ越しの月面は素晴らしく、ああ地球の影が月面に落ちているんだということがリアルに感じられましたし、一眼レフはデジスコに比べて操作性がよくて撮影も簡単でした。

こうして撮影するとあとで月食の興奮を振り返ることができてとてもいいわけですが、やっぱり肉眼で見るのとは大違いで、スコープのよさを再認識しました。
今回は皆既月食中に天王星食が起こるということでした。最初はどれが天王星なのかさっぱりわかりませんでしたが、TwitterのTLを参考に見当をつけて観望継続。そして天王星が月に飲み込まれていく瞬間をしっかり見ることができて感激しました。天王星は上の連続写真にも辛うじてい写っています(下から3段目)。拡大したのが下の画像。

矢印が月に隠れる直前の天王星です。おそらく天王星を意識して見たのは最初で最後のことだと思います。青みがかかっているのもわかりました。
皆既月食中に惑星食が起こるのは日本で1580年7月の土星食以来で、次回は322年後の2344年7月の土星食ということですから、大変いいものを見ることができました。
次に日本全国で見られる皆既月食は2025年9月8日、2時30分から3時53分と遅い時間ですが、楽しみです。

皆既月食の3日後、この日は月と火星とが接近していました。ずっと鳥クラスタでしたが、天文もとてもいいなと思います。、
11月畦道2回目
2022年11月17日記

11月の畦道は2回目です。上旬、午後3時半から1時間、気温は15℃。

気温はまあまあ高めでしたが、トンボは全く、チョウもほとんど見ませんでした。

鳥はヒヨドリを中心に、モズ、セグロセキレイ、キセキレイジョウビタキ、スズメ、ハシボソガラス。この頃Twitterでは、ジョウビタキ以外にもカシラダカやベニマシコなどの冬鳥の到着が報告されていましたが、当地ではまだ早かったようです。

すっかり秋の畦道の主役になってしまったセイタカアワダチソウです。これだけ耕作放棄地が増えてると見られる鳥の種類が少し変わってくるのかとよく思っているのですが、今のところあまり違いを感じていません。

2日後に皆既月食を迎える月齢11の月が志賀の上空に姿を表していました。
久しぶりに姪っ子との山
2022年11月13日記
11月初旬、姪っ子が弟と一緒に帰省してきました。新型コロナの関係で3年ぶりに会いました。大学では山岳サークルに所属してバリバリ山を登っているそうです。山の準備はしてこなかったのですが、天気もいいしということで、姪と弟と私の3人で歩くことにしました。

展望と紅葉の山がいいというので、行き先は近くの某里山に決定。

北アルプスが見える所が希望のようでしたが、あいにくここらの山からはアルプスは難しいのです。それでも天気には大変恵まれて、東方連山や浅間山などが見えたのでOKでしょう。下山ルートは別にとってぐるっと周遊しました。

2時間程度の山歩きでしたが、楽しいひと時を過ごすことができました。小さい頃、私がいろいろな山に連れて行ったことが、大学生になって山を歩くようになったきっかけということなので、嬉しい気持ちはあるのですが、遭難には本当に気をつけてほしいと思うおじさんなのでした。
カメノコテントウの越冬
2022年11月13日記
とある小さな建物のコンクリートの壁部分に、ナミテントウとカメノコテントウが集まっていました。カメノコテントウはこの夏戸隠でたまたま見ましたが、クルミハムシやドロノキハムシなどの幼虫を食べるため、主に畦道を歩いてる私にはあまり縁のない虫です。なので出会えると嬉しい大型のテントウムシです。

以前NHKの「ダーウィンが来た」で、テントウムシが家の白い壁に集まってくるということをやっていたように思います。これもそれと同じく越冬に向けての集合なのでしょう。TLでフォローしている方が、農作業中に服に向かってたくさんのテントウムシが飛んできたということをつぶやかれていましたが、それも同じく「白」の服だったそうです。
白いということと越冬しやすさにどういう関係があるのでしょうね。

カメノコテントウは、少しいじると眼のすぐ後ろにある黄色紋のあたりから、赤い汁を出します。なんだか血のように感じてしまって、ちょっと抵抗があります。
リンゴが光る秋の畦道
2022年11月13日記
11月初旬の畦道です。

午前11時前から1時間ほど歩きました。気温は9℃。

リンゴがピカピカ光る、いい天気の日でした。畦道とはいえ、稲を作っている田んぼはかなり少なくなってしまい、沿道の環境の9割くらいは耕作放棄地とリンゴ畑です。

畦道沿いの木立がいい色になっていました。ここは過去に結構いろいろな鳥が見られている場所なので、毎回きちんとチェックします。オオタカ、ノスリ、アオシギ、トラツグミ、クロツグミ、シロハラ、ベニマシコなどなど。今回は特に収穫はありませんでした。

木立の中に入って見上げると、まさに秋の色でした。

道端というか畑の端に植えられている花に、キタテハ。

休耕地にモンキチョウ。数はかなり多いです。

ウラナミシジミはまだ頑張っています。ほかにヤマトシジミ、ベニシジミ、ツマグロヒョウモン、キタキチョウ。

不明双翅目。コガネオオハリバエあたりでしょうか。
トンボはすっかり姿を見せなくなっています。

鳥は、スズメ、カワラヒワ、ヒヨドリ、トビ、ハシボソガラス(トビにモビング)、オナガ、キセキレイ、ジョウビタキでした。

晩秋のミノウスバ
2022年11月13日記
ここから11月の記録です。この日は庭にたくさんミノウスバが飛んでいたので、写真を撮りました。

これまでの例ですと、庭で見られるのは数日ですので、暇な休日が重ならないとそのシーズンは撮らずじまいになってしまいます。

この日はマサキの周りにかなりの数が飛んでいました。

交尾も観察できました。

撮影中は気が付きませんでしたが、枝にびっしり卵が産み付けられていました。食害の程度は大したことがないので、我が家では特に駆除などはしていません。なので来年もきっと日が合えばミノウスバを見ることができるでしょう。