野外手帳
-2022年4月
自宅待機
2022年4月30日記
そういうわけで大型連休が始まりましたが自宅待機です。庭で写真を撮っています。

4/28、4/29、4/30と自宅でやきもきとして過ごしているだけではなんなので、野外手帳と写真倉庫を計15件更新しました。これで4月中に撮った写真のアップロードはとりあえずおしまいです。
夏鳥本格渡来の少し前
2022年4月30日記
4月下旬の近所のいつもの森です。最初から最後までずっとメジロが鳴いていました。あと、おそらくアオゲラのドラミングが時折響いていて、とても春らしいすてきな森歩きになりました。

目的はキビタキやエゾムシクイ、センダイムシクイなどの初認でしたが、結果的には果たせませんでした。夏鳥ではクロツグミとサンショウクイを確認。クロツグミはオスメスを視認できました。

撮影できたのはシジュウカラ。

なにやらくわえています。イモムシでしょうか。

ヤマガラも撮れました。

最近森の中で見かけることがでてきたネコ。鳥たちをはじめ小動物に影響があるのではないかと心配です。

タチツボスミレはそろそろ花期を終える感じです。葉の存在感がかなり増してきました。

道端の花の主役はカキドオシにチェンジです。

ムラサキケマンはちらほら。これからです。

湿った場所にはネコノメソウ。

まだまだ咲いているウグイスカグラ。

これから咲こうとするヤマツツジ。

宇宙人っぽいアオキ。前来たときには産毛に覆われていたコナラの若葉は、どんどん成長をしていました。

実はこの日、朝から母の様子がいつもとは少し違っていました。午後になって落ち着いた印象があったのでこの森を歩いてしまったわけですが、結果的に帰宅後に救急搬送をお願いすることになりました。自分たちだけではそれほど状態が悪いとは気づけず、訪問看護師さんの判断がなければ大事にいたるところでした。
搬送後も予断を許さない状態が続いているので、しばらくいろいろとお休みです。変に家にいる時間だけは長いので、溜まっていた写真をまとめてアップしました。

昔は花を見ていなかった
2022年4月30日記
「地元カタクリ山」とは別の4月下旬の地元里山。

登山口にはヤマザクラ。足元にはタチツボスミレ。


少し湿った場所にはムラサキケマンが咲いていました。

山道は新緑がまぶしく、ヤブサメの声があちこちから聞こえてきていました。若いときのような広がりのある音には聞こえないのはとても残念ですが、まだ聞こえることはありがたいことなのかもしれません。ただ当時聞いた声は心の中には残っていて容易に思い出すことはできます。

大好きなリョウブの若葉も美しかったです。

キブシ。

ヤマブキ。

モミジイチゴ。


そして今日この山のめあてのイカリソウ群落。


そしてもう一つの目当てはこのクロモジの花。
この山道はそれこそ中学生の頃から歩いているところで、確か、初めてヤブサメやオオルリを見たのもここだったと思います。ただその時は鳥だけでした。こういう花に目が留まるようになったのは最近のことです。
鳥的には、目標の一つだったオオルリの初認を果たし、これまで声しか聞けていなかったクロツグミを今季初めて見ることもできました。

近くで見ることができたのはこのコガラくらい。

山麓に戻って田んぼの中の道。

見上げるとノスリ。最近はノスリを見る機会が多いと感じます。

電線の上で、私を介して向かい合うキセキレイのペアを見て、この日の山歩きはおしまいです。
ヒオドシやサシバ
2022年4月29日記
「地元カタクリ山」の続きです。4月下旬の里山歩きのカタクリ以外の記録です。

山麓の果樹園ではモモが咲き始めていました。

ウメ、サクラ、モモ、リンゴと果樹の花の季節が続きます。
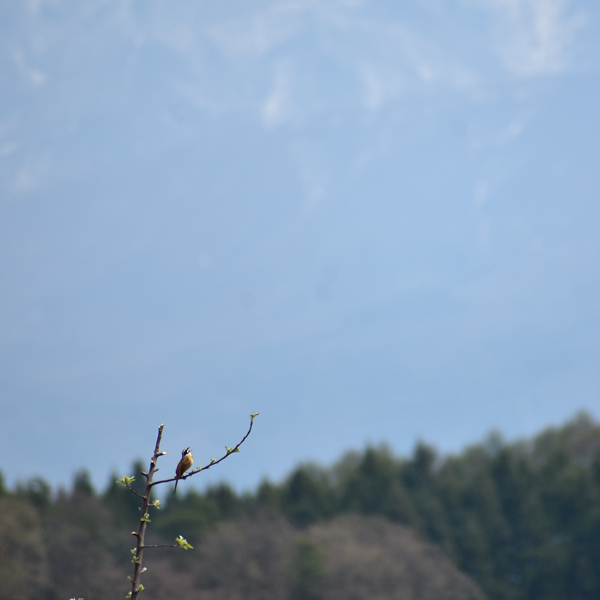
ここではホオジロがさえずり、またカシラダカもまだ残っていました。

北へ向かうヒヨドリの群れを見たり、ハシボソガラスのモビングに逆襲するノスリを見たりしたあと、山道に入りました。

山道での主役はカタクリだったわけですが、新緑もかなり見事。

足元には(いつもきちんと調べていない)シダも芽を伸ばしていました。

そのほかの花々。


蝶はアカタテハ、ルリビタキ、そして山頂でヒオドシチョウ。今季初めてまともにヒオドシチョウの撮影ができました。

林道に回ると、ここではスジボソヤマキチョウを見ることができました。カタクリが多いので、ヒメギフチョウとの組み合わせを期待してしまうのですが、ここで観察したことはありません。食草がないんでしょう。

鳥的には山を降りてからがハイライトでした。期待していたサシバを見ることができました。そのほか、夏鳥ではヤブサメ、サンショウクイ、クロツグミ、ビンズイを観察しました。すべて初認です。
地元カタクリ山
2022年4月29日記
4月下旬、地元里山でもようやくカタクリの季節になりました。

日当たりがあまりよくないところでは、咲き始めという感じでした。この山のカタクリがちょうど見頃になるのは年によってばらつきがあります。今年はぴったりでした。

地面に這いつくばって写真を撮ります。人はめったに来ない道なので、変なかっこうをしていても大丈夫です。

少し歩くと、ややまとまって咲いている群生地に行き当たります。

この風景を独り占めできるのはかなりぜいたくなことです。



山頂直下の日当たりのよい場所では、花弁の痛みが進んでしまっていました。続きはこちら。
ノビタキやノスリ
2022年4月28日記

前回の1週間後の畦道散歩です。

この日はなんといってもノビタキの通過に行き会えたのが嬉しかったです。週に1,2度の畦道散歩なので、通過していくノビタキを観察するにはタイミングが合わない無理です。遠くて写真はこんなのしかありませんが幸運でした。

いつもの面々。ツグミがまだいました。スギのてっぺんに止まっていたノスリは、このあとあたりを飛び回る姿を見せてくれました。

かなりかっこいいです。

用水にはカルガモがいました。

美しい芽吹き。春はいい季節です。その木の中断でモズがさえずっていました。

この日はパピリオを初使用。アブラムシをむしゃむしゃ食べるナナホシテントウの観察が楽しかったです。遠くも近くもよく見えない、近眼で老眼のお友達にはかなりおすすめです。
芽吹きの季節
2022年4月28日記
4月上旬の畦道散歩です。

これを書いている4月下旬はすでにリンゴは開花していますが、この時点ではまだ花びらも見えていませんでした。

ウメはちょうど見頃。

サクラは5分咲といったところでした。

春の楽しみは蝶が飛び始めることです。これはモンシロチョウ。

ルリシジミ。他にはモンキチョウを見ました。

雑木の林床ではシロハラが大きな音を立てて落ち葉をひっくり返していました。
そのままいつもの近所の森に接続。

ニオイスミレはおしまいです。葉っぱだけになっていました。

代わりに咲き始めたのはタチツボスミレです。

ごくごく普通の種類ですが、本当に美しい色のスミレだと思います。

芽吹きが始まり、華やかな感じがします。

中でもコナラの新芽の美しさに強くひかれます。


細かな毛が光を受けて輝いて見えます。


真っ先に咲き始めたウグイスカグラはまだまだ頑張ります。

夕日が傾く帰り道では、用水の端でヒヨドリが何かを探していました。

チョウの吸蜜
2022年4月17日記
いつもの近所の森歩きの後、里山山麓に転進しました。

登山口のサクラはこんな感じ。やっぱり少し遅めです。

タチツボスミレはなぜかこちらのほうが早く、あちこちにたくさん咲いていました。

そしてタチツボスミレを吸蜜するスジボソヤマキチョウの観察に成功。冬越ししたたくましい色に感動です。

同じくタチツボスミレを吸蜜するキタキチョウ。彼らも成虫越冬組です。

花の時季以外は気づくことのないウグイスカグラ。花期が早いので、山の中で目立ちます。

コマルハナバチ(でいいと思います)が吸蜜に訪れていました。次から次へと花を回っていく様子を見ていて、よく吸蜜した花を覚えているなと思いました。見ていた限り、ダブることがありませんでした。

ウグイスカグラと並んで真っ先に山で咲くダンコウバイ。

チョウジザクラ。これは、えっもう咲いているの?という印象でした。

クロモジ発見。この花を見るのも楽しみです。
スジボソヤマキチョウとキタキチョウの他、ヒオドシチョウも見ました。ヒオドシを見ることが今回の一番の目当てでした。残念ながら写真は撮れませんでした。

撮れたのはルリタテハ。

そしてイカリモンガ。イカリモンガってこんな早くにも出てくることを初めて知りました。

画像はカナヘビ。鳥はシジュウカラ、ヒガラ、ヤマガラ、エナガ、コゲラ、アカゲラ、ヤマドリ、ノスリ、メジロ、ヒヨドリ、ツグミ、ミソサザイ、ウグイス、ホオジロ、シメ、アトリ、マヒワ、カワラヒワを観察しました。
サクラ開花の4月10日
2022年4月17日記

気象台発表より1日遅れて、いつもの近所の森近くのサクラが咲き始めました。

3月はウグイスカグラくらいだった芽吹きが一気に始まっていました。

中でも目を引く美しさはコナラの新芽。

写真を撮ったときには気づきませんでしたが、虫の卵が写っていました。

まだ食べたことがないハリギリ。まあこの森では山菜を採る気はないです。

これも3月には見かけなかったウバユリの若葉。もうかなり葉を伸ばしてつやつや光っていました。

名前はわかりませんが、シダ系もぐんぐん展開中でした。

タチツボスミレはまだ葉だけの株が多かったです。

でも一部は咲き始めていました。本当にすてきな色です。

ネコノメソウ咲き始め。

山に入るとどこでもよくみかけるスゲの仲間。名前がわかりません。

グーグルレンズ先生に聞いたらワタスゲと教えてくれました。そんなわけはないわけで、とりあえずカンスゲの仲間ということにしています。

3月はつぼみが多かったウグイスカグラは見頃を迎えていました。

ダンコウバイ。
この森にはキブシもあります。多くはないですが。

アトリをまだ見ることができました。
ウメ満開の4月9日
2022年4月16日記

先週の土曜日、長野市のソメイヨシノの開花宣言が出ました。近所の木はまだこんな感じでした。

それから1週間。また土曜日がやってきましたが、もう見頃は過ぎてしまいました。ウイークデーに一気に満開になり、そしてすぐに散り始め。今季はまともなお花見ができませんでした。

先週はまだウメもいい感じでした。長野の春は本当に駆け足で通り過ぎていく、そんな印象が今年は特に強いです。

ウメにメジロが来ていないかとあちこち見て回りましたが、それは叶いませんでした。

その代わり、カワラヒワとのコラボ。

枝がかなりごちゃついてしまったものの、ヒヨドリとのコラボも撮れました。

畦道の花はかなり勢いを増してきていていました。

ハコベの海の中で何かを食べているヒヨドリ。

びっしりと咲くホトケノザは、あまりにも普通種過ぎますけれど、かなり見事だと思います。

新たにカラスノエンドウ開花。スイバの花穂はかなり伸びました。

用水沿いではハクセキレイをセグロセキレイを見ました。ツバメはずっと前からここにいたかのように当たり前に飛び回っていました。

小さな雑木の林には尾曲エナガとシジュウカラ。直前に頭上をオオタカが飛んで、これはその警戒が解けたあとの写真です。

そのほか、ハシボソガラス、ムクドリ、モズ、スズメ、シメを観察しました。ツグミはだいぶ少なくなりましたが、まだ見ることができました。

