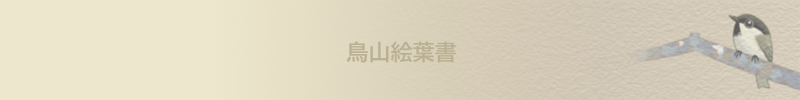野外手帳
-2021年8月
ベランダのセミ
ベランダにセミが落ちていました。

ひっくり返して背中を見てみると、エゾゼミではありませんか。
このあたりでは鳴き声を聞いたことがありません。山のセミだと思っていたので、ベランダに落ちていたのはとても意外でした。
もう一匹落ちていました。

こちらはミンミンゼミでした。
これで8月の記事はおしまいです。
2021年9月なかごろ記
サトイモの謎

サトイモの葉の上にはいつもありがたくさんいます。毎日います。でも食べ物になるようなものは見当たりません。なんでだろうと思っていました。
検索してみると、アブラムシがサトイモにつくことが多いのでアリも来るという話題がいくつか引っかかります。でもアブラムシはぱっと見は見当たりません。よく探すといるのかもしれません。
2021年9月なかごろ記
戸隠晩夏花見編
戸隠晩夏鱗翅編の続きです。

最初の画像はアキアカネですが、これより後は花などでまとめました。

この時季の戸隠では外せない花見は、なんといってもこのオオシラヒゲソウです。

普段は戸隠に来ても戸隠奥社参道を歩くことはほとんどないのですが、この花は奥社参道にたくさん咲いています。

かがんで写真を撮っていると多少人目が気にならないことはないです。

高台園地より少し奥に行くとアケボノソウの群落がありました。この花も見逃せない花の一つです。姿にも名前にもたいへん心惹かれます。

それにしてもなんというデザインなのでしょう。感嘆します。

杉の森で見つけたアケボノシュスラン。

同じ「曙」を名前に持つ花でも上のアケボノソウとはかなり趣が違います。この花の色はとてもいい色だと思います。

植栽のレンゲショウマ。アケボノソウに勝るとも劣らないデザイン。色も質感もすてきです。

何枚とってもこれというカットがありません。撮影が難しい花です。

アズマレイジンソウ。こうして群れ咲くと見事です。

アップだとどこにピントを合わせたらいいのかよくわからない花で、これも気に入ったように撮るのは難しいです。

大好きミゾソバ。里でも見られますけど、山では一足先に見られて嬉しく思います。

トリカブトの仲間。この花は見た目通りの色に撮れません。赤味が抜けて青く写ってしまいます。カメラの背面液晶で見る色と、同じ画像をPC画面で見る色も違います。もう何がなんだかわからなくなるので、記憶を頼りに色をいじっています。

これはちょっと濃くしすぎたかも。

エゾリンドウも青く写ってしまったので少し赤を足して修正。

今が盛りのツリフネソウ。

キツネフリはアカアシカスミカメ付き。

いろんな実。青いのはルイヨウボタンでしょうか。

もうほとんど終わっていたジャコウソウ。手持ちの植物図鑑は何冊かありますが、なかなか載っていない花で、最初は名前を突き止めるのに苦労しました。
2021年9月なかごろ記
戸隠晩夏鱗翅編

8月末の戸隠森林植物園です。

ミドリヒョウモンの天下でした。

見かけるチョウの9割以上がミドリヒョウモンと言ってもいいくらいでした。

その他のチョウ。ヒメキマダラヒカゲ、メスグロヒョウモン、サカハチチョウ、たぶんウラギンスジヒョウモン。

蛾では一番多く見たのがこのツバメエダシャクの仲間です。顔はほぼ白いのでウスキツバメエダシャクや亜高山性のノムラツバメエダシャクではなく、後翅の筋がくの字に曲がっていないのでヒメツバメエダシャクではなく、翅の筋は茶色がかって見えるので、フトスジツバメエダシャクやコガタツバメエダシャクでもなさそうで、そうするとシロツバメエダシャクでしょうか。

とここまで調べたとき、オスの触角が櫛状になっているのはシロツバメエダシャクだけだという記述を見つけました。というわけでこれはシロツバメエダシャクでよさそうです(上写真左下)。

美しいアオシャク系。

クロホシフタオ。

バラシロエダシャクっぽいです。

シロオビクロナミシャク。

フタオビシロエダシャクあたり?違うっぽいですけど。

アカトビハマキ。ウストビハマキ、スジトビハマキなど近縁種の中で顔が白いのは本種のオスだけとのこと。

そして苦手なマダラたち。嫌いなわけじゃないです。後半に続きます。
2021年9月なかごろ記
雨の小径
ちょっと空いた時間に小さな山の小径へ。

雨が降ったりやんだりで、傘を差して歩きました。

ツリバナの実が割れていました。この山にこんなにたくさんツリバナがあるとはこれまで気づきませんでした。

ツリバナには、たくさんのキバラヘリカメムシがくっついていました。

トンボは相変わらず難しいです。マユタテアカネでいいんでしょうか。

2021年9月なかごろ記
主に蛾を見る午後歩き

ゲンノショウコが咲き始めたいつもの某所です。「現の証拠」って改めて字にするとなかなかすごい名前です。

秋らしい花とか実とか。

アケボノシュスランを見つけました。夏にはジンヨウイチヤクソウが咲く場所です。

ヒメとの区別が難しいですが、これはコジャノメでいいと思います。

今季は少ないキンモンガ。翅の白い部分ってこんなに目立ちましたっけ。

ホソバナミシャクでいいかな。食草はタラノキということなので、もっと見かけてもいい蛾だと思ってしまうのですが、たぶん初見です。蛾のどの種類が初見かどうかということはちょっと把握できていないです。

ハグルマエダシャクかマルハグルマエダシャクのどちらかと考えました。蛾は葉裏に止まる種類が多いので、昼間は見つけるのも写真を撮るのも難しいです。

相変わらずわからないマダラエダシャク系。ユウマダラエダシャクでないことだけはわかります。みんなで作る日本産蛾類図鑑には「前翅前縁中央にある灰色の斑紋の中に黒い輪っか状の紋がなければ」ユウマダラエダシャクとありますので。

ウスイロカギバ。これは覚えました。

おなじみイカリモンガ。この蛾の名前を調べるところから蛾の世界の深淵を覗くことになったのでした。

クロホシフタオ。

ヒゲナガキバガの仲間。

アオイトトンボかオオアオイトトンボ。

美しいメタリックです。

ゴマダラシロエダシャクの幼虫のようです。

エゾゼミの生と死。歩き始めは曇っていて気温も21℃と低めでエゾゼミの声はしていなかったのですが、日が差してくると彼らの爆音が復活しました。以上、8月中旬の記事です。
2021年9月なかごろ記
謎のレース
前回とは別日です。雨上がりの畦道。

鳥はスズメ、ムクドリ、オナガ、キジバト。ツバメはどこに行ってしまったのかという感じです。

写真は撮れませんでしたがキツネを見ました。以前このあたりでは疥癬におかされたキツネを見ました。今回のは健康な個体でした。
キツネを見るということはうれしいことですが、最近愛知でエキノコックスが定着してしまったのではないかというニュースを見て、この辺りでもそうなってしまうことを恐れます。

前回いろいろな虫たちを観察できた未舗装の畦道へ。

また別のハチ。アカスジツチバチかキオビツチバチのようです。マクロレンズをつけていかなかったので(35ミリ単焦点)、大きく撮れていません。画面上で拡大すると頭にも黄色い部分があるように見えるので(下の写真)、アカスジツチバチとしておきます。

なかなかかっこいい蛾を見つけました。

フタテンオエダシャクのようです。食草はネムノキ。

さて今回の畦道歩きでの謎はこのレース状の糸です。エノコロの穂を覆うようにかかっていました。

しかもそれが結構な長さ、数メートルに渡って草の葉先や穂先を伝って続いているのです。

クモの糸ではなさそうだし、ツイッターで聞いてもみましたが、正体がわからずじまいです。
2021年9月はじめ記
8月の畦道の虫たち
8月の畦道、トンボ以外の虫偏です。

まずは甲虫。左上からコクロコガネでいいでしょうか。あとコアオハナムグリ、マメコガネ、クズの常連コフキゾウムシ。

ハチでは、まずこれ。オオフタオビドロバチでいいと思います。

ミカドトックリバチかムモントックリバチのどちらか。

これはフタモンアシナガバチでしょうか。

近寄ったらヤバそうなアブ。複眼が緑なのでウシアブと考えてみました。

鱗翅たち。ベニシジミ、ヤマトシジミ、ウラナミシジミ。

次は半翅。ヒメジュウジナガカメムシかジュウジナガカメムシ。右はマルカメムシ。

ステキデザインのキバラヘリカメムシ。

最後は直翅でショウリョウバッタ。
2021年9月はじめ記
8月の畦道

歩き始めてすぐ、小路のフェンスにオナガサナエ。

警戒心が薄く、かなり近寄って撮影ができました。

少し離れた場所でも見かけました。

シロバナサクラタデが咲いていました。これからはタデ科の花が楽しみなシーズンです。

キカラスウリの花が咲いていました。

素晴らしいデザインに改めて息をのみます。

ノブドウが色づき始め。

ヤイトバナ、クズ、ツユクサ、ヨウシュヤマゴボウなどの茂みにはいろいろな虫がいました。つづきはこちら。
2021年9月はじめ記
8月の庭

ニラの花が咲き始めです。9月の虫たちにとってはいい蜜源です。

ヤイトバナは今が盛り。

ガガイモもいい感じです。

そのガガイモにはシロテンハナムグリが来ていました。

ヤマトシジミ。ゴマシジミとヤマトシジミは似ていると思っていましたが、実際にゴマシジミを見てみると全く違いました。

ゴーヤの花の中になんとかアリ。花と虫を見ていると何十分も過ごしてしまいます。
2021年8月おわり記
ゴマシジミとシワクシケアリ
ルリモンハナバチと同じく、これも前から見たいと思っていたゴマシジミを某所にて。昨年もほぼ同時期にトライしましたが観察できませんでした。今回は計4頭ほどを見ることができました。

もう少し近い距離で見たかったのですが、絶滅危惧II類の希少なチョウを見ることができただけでもとても貴重な体験だったので、それは贅沢というものです。翅裏の地色の茶色と白く縁取られた黒紋とのコントラストが美しく感激しました。

食草(ワレモコウ)があるだけではだめで、シワクシケアリとの関係がなければこのチョウは生きることができないという自然の不思議さ、巧妙さを改めて思うわけですが、少し調べてみると気になる記述が見つかりました。以下引用です。
----------
ゴマシジミとオオゴマシジミの幼虫はそれぞれ異なるひとつのシワクシケアリ系統のみに寄生しており、絶滅が最も危惧されるゴマシジミ 属の発生地では特定の遺伝的系統の寄主アリが激減し、別の系統のアリが生息していること(ゴマシジミ属と寄生アリの相関性)が判明した。
----------引用ここまで(大阪府立大学プレスリリースより)
シワクシケアリがいればいいというわけではなく、見た目では区別のできない4つの遺伝的系統を持つシワクシケアリのうち、寄生している系統のアリがいなくなってしまえばゴマシジミも絶滅する運命だということです。これは厳しい。
つまり、そのシワクシケアリを保全しないとゴマシジミの保護はできないということなのです。ではどのように?
シワクシケアリについて検索してみると「寒冷地では普通」とか「国内の山地に広く分布」「朽木を住処にしている」「湿地に多い」ということが書かれたページは見つかりますが、特に減っているという記述は見つかりませんでした。となるともうこれは人間の知恵の及ぶところではないのかもしれません。
2021年8月おわり記
ルリモンハナバチ
前から見たいと思っていた(ナミ)ルリモンハナバチ。所用で立ち寄った場所で思いがけず見ることができました。

慌てて車までカメラを取りに戻りました。一箇所で落ち着いて吸蜜していたので撮影することができました。美しいハチです。

検索してみて「ナミ」がついている場合とついてない場合とがあります。その違いはちょっとよくわかりません。ブルービーとも呼ばれているようですが、ルリモンハナバチのほうがいい名前だと思います。
2021年8月おわり記
戸隠8月その3 蛾のデザイン
戸隠8月 ノブキの小径
戸隠8月その2 花と実と
のつづきです。鱗翅編。

比較的多かったのはサカハチチョウ。

アサギマダラも数回見ました。

オオウラギンスジヒョウモン。咲き始めたタチアザミでの吸蜜です。

ミドリヒョウモン。

スジグロシロチョウでいいでしょうか。

キアゲハ。

ミヤマカラスアゲハ。今季は少なく感じます。ぐるっと園内を1周して2頭だけ。

かなりすれているけどオオチャバネセセリでいいと思います。

とてもたくさんいたシロオビクロナミシャク。敏感で撮りにくい蛾です。でもかなり好き。
シラフとの違いは翅縁の白がまだらになるかどうかだと承知していましたが、ほかにも「白帯」が本種では前翅の後角に向かうのに対して、シラフは外に広がる感じがあるということです。
もう一つ似ている種類のシロホソオビナミシャクは、前翅の縁は翅頂と後角が白、後翅の縁は一様に白ということで、これは自分用のメモ。

美しいアオシャク。ヒメウスアオシャクあたりではと見当をつけてはみました。

フトベニスジヒメシャクでいいでしょうか。前翅と後翅のラインがこうしてぴったりそろうことが、とても不思議です。展翅した図鑑ではこのすごさが今ひとつわかりませんが、こうして生態写真にすると、あらためて感動します。蝶ではあまりこういうデザインはないと思うのですが、蛾では前翅と後翅の模様がセットになっている例は多いですよね。

スカシサン。初めて見ました。食草はサワフタギなど。そういえばこのあたりでサワフタギの実を見かけたことがありました。

これはよくわからなかった人たち。左は例のよくわからないヒゲナガキバガの仲間です。

そしてこれも相変わらず名前はよくわからないけどたくさんいるマダラエダシャク系。葉の裏にとまる蛾が多い中で、白く目立つ彼らが平気で葉の表に止まっていられる理由が知りたいです。鳥の目を欺くなにか秘密があるのでしょうか。
2021年8月おわり記
戸隠8月その2 花と実と
戸隠8月のつづきです。

この時季楽しみなのは植栽とはいえレンゲショウマの清楚な美しさです。

あちこちでみられるジャコウソウ。

アズマレイジンソウもそろそろです。

アズマなのかただのレイジンソウなのか、私には区別ができません。公式ページなどでここのレイジンソウはアズマとなっているので、それに倣っています。

戸隠でもミゾソバのシーズンイン。

花期が長いエゾアジサイ。花弁というか萼が裏返っているのはなぜ。

トモエシオガマ。

タマガワホトトギスはこんな感じです。

いろいろな実。まだ青いツリバナが割れるのがこれからの楽しみです。

いろいろな実の中で一際目をひくトチバニンジン。

ベニタケの仲間っぽいキノコもあちこちで見ました。
2021年8月おわり記
戸隠8月 ノブキの小径
戸隠森林植物園に向かう途中、えお盆でもないのに渋滞?と思ったら、鏡池方面渋滞でした。

植物園の駐車場は余裕がありました。

鳥はアカハラを見たくらいで、あとはクロツグミ、ウグイス、コガラ、ホトトギスの声だけ。戸隠のアカハラってとても減ってしまったと感じます。軽井沢でも激減らしいんですけど。

先日の某所と同じく、ここでもノブキの結実が始まっていました。

でもまだ咲いている株のほうがずっと多くて、遊歩道の周りを飾っています。

ノブキにアカアシカスミカメを見つけました。

カワトンボの仲間。

ヤマトカワゲラ。何度か見かけました。山地の渓流で見られる種類だそうです。
2021年8月おわり記
アブラゼミは翅を残した

玄関にアブラゼミが落ちていました。もう飛ぶ元気は残っていないようでした。

翌日、アブラゼミの前翅が玄関に残されていました。
2021年8月おわり記
秋の始まり
夏の終り、鱗翅編です。

今シーズン2回目のヒョウモンエダシャク。

少なく感じるキンモンガ。ただ単にタイミングが悪いだけのようにも思いますが。

ウスキオエダシャク。繊細で精緻な模様が美しいです。

自らを枯れ葉と信じて、近づいても微動だにしないウスイロカギバ。本当によくできているって感じです。

ウンモンクチバでいいと思います。食草はヌスビトハギだとのこと。この辺りはヌスビトハギはとても多いのですが、目立たない色彩なので見逃しているのかもしれないです。

アトボシエダシャク。発生期間は結構長い印象です。

夕方になって薄暗くなってきた森で、美しい模様を見せるヨコジマナミシャク。葉の裏にとまるので撮影が難しいです。

キベリシロナミシャク。食草の一つ、ノリウツギはここにはたくさんあります。

ウスオビヒメエダシャクの裏側。これは覚えました。

その他の面々。左上のマダラエダシャクはヒメかなと思いますが、よくわかりません。これはとてもたくさんいました。5m進むごとに1頭見るという感じでした。他はよくわかりません。

これもよくわからないです。左のヒゲナガキバガの仲間はよく見る種類で、でもweb図鑑には該当する画像がありません。ツイッターで見つけたオオキイロホソバヒゲナガキバガとかが雰囲気としては近いと思いました。黄色くないですけどね。
さて、ちょっと意外だったのはキアゲハの幼虫がたくさんいるセリ科の植物(オオバセンキュウかなにか)を見かけたことです。

キアゲハはニンジン畑にいるという思い込みがなぜかあって、どうしてキアゲハが森の中にもいるのかちょっと不思議に思っていました。でもよく考えてみればこちらが本来の食草なわけです。

でもこれまでセリ科の植物を見かけることはとても多かったのですが、キアゲハの幼虫がついているのを見たことはありませんでした。
2021年8月おわり記
夏の終わり
下界よりは5℃ほど低いいつもの某所。車を降りたとたん、エゾゼミの声がフルパワーで押し寄せてきました。

熊鈴の音さえかき消されるほどの爆音。声を頼りに姿を探しますが、抜け殻は多数見つかるものの、なかなか見つかりません。やっとのことで枝先に止まっているセミのシルエットを発見しました。家に帰って拡大してみると黄色いラインが半周しているので、やはりエゾゼミでよいようです。

ノブキは結実し始めていました。この種の形は結構好きです。

ヌスビトハギは咲いているものと、実になっているものとが混在していました。

ヌスビトハギの花言葉は「略奪愛」だそうで、花言葉って本当にいい加減だと思います。

キンミズヒキなど秋を告げる花が目立ってきました。左下はミヤマタムラソウです。

これは出番を待っているサラシナショウマ。これが咲けば夏は終わりというイメージです。

そしてここでも大好きなミゾソバの花期の始まり。

ミゾソバも湿った場所の花ですが、ツルボもそう。

花の先にはアカアシカスミカメがいました。

マユタテアカネ。

アオイトトンボでしょうか。よくわかりません。

ヤマトシリアゲでいいと思います。鱗翅はこちら。
2021年8月おわり記
朝のヒメシロモンドクガ
妻にベランダに蛾がとまっていると教えてもらった朝7時。

ヒメシロモンドクガです。幼虫はどこかで見たことがあるような気がします。なんともおどろおどろしい雰囲気に満ちている毛虫ですが、成虫は地味系です。
2021年8月おわり記
ゲレンデを歩いて当たり

空いた時間を使って、スキー場のゲレンデを一登りしました。

ホオアカがいました。結構久しぶりに見ました。そして写真にはありませんが、なんとオオジシギがいました。これはもうすごく久しぶり。これでもうここに来た意味があった!と思いましたが、もう少し歩いてみることにしました。

すごく多かったのがこのジャノメチョウです。私が歩く範囲でのジャノメチョウ亜科はクロヒカゲやキマダラヒカゲ系、ヒメウラナミジャノメなどが多くて、めったにこのジャノメチョウは見かけません。
2021年8月おわり記
マイナー高原虫探し
この日も八方行きの日に続いて平日休み。人より少し早く夏休みに入ったので、比較的行動に自由がききます。

j時間的には余裕があったのですが、遠くはやめて近くの高原へ行く程度にしておきました。ここはマイナーな場所なので人に会う心配はまずありません。コロナ禍なので、どうしてもこういうところは気にしてしまいます。

もうミゾソバが咲き始めていました。秋がやってきます。

美しいドクゼリの群落。ここでの目標はこのアブを見ること。

キヒゲアシブトハナアブです。環境がよいところでしか見られないという種類なので、ここに来たら生息を確かめたい種類なのです。

ツマグロキンバエもいました。
さて蛾ですが、思ったよりは種類を見ることができませんでした。でもこれ図鑑で見たことある!という蛾を2種観察できました。これはとても楽しいことです。

まずはこれ。キエダシャクです。

それからマエアカスカシノメイガ。

これは同定できていません。スガ科の仲間です。最初はクモの巣に引っかかってしまっているのかと思いました。

蝶は不作で、このミドリヒョウモンとアカタテハくらいでした。

トンボはミヤマサナエでいいでしょうか。

それとアキアカネです。

トモエソウ、シキンカラマツ、ツリフネソウ、キフリツネ。
鳥は姿は全然見ることができませんでしたが、クロツグミ、アオジ、アカゲラ、コゲラ、キジバトを確認しました。
2021年8月おわり記
八方下山
日帰りチャレンジのつづきです。

クガイソウが美しい八方池周辺です。この撮影ポイントは大好きです。

時間がないのでちょうどお昼時ではありましたがここでの昼食は(とはいってもコンビニおにぎりでしたが)あきらめて、下山してから車の中で食べることにしました。

ぐるっと一周してすぐ下山にかかります。

さよなら不帰ノ嶮。

クモマミミナグサ、ホソバツメクサ、タカネシュロソウ。

ミヤマウイキョウ。

自分では絶対見分けられないハッポウウスユキソウ。

さよなら白馬三山。

鎌池湿原にちょっと立ち寄り。ホツツジの花が咲き、コバイケイソウが結実していました。
帰り道の土砂崩れ交互通行地点の渋滞は大したことがなく、予定時刻の20分前には帰宅ができ、今年のアルプス日帰りチャレンジも無事成功しました。
2021年8月おわり記
日帰りチャレンジ
毎年恒例、平日休みのアルプス日帰りチャレンジです。デイサービスに母を送り出したあと、9時半に家を出て、デイサービスの迎えがある16時までには帰宅するという縛りの範囲内で、アルプスの片隅をなんとかかすめてこようという個人的イベントですが、今年は8月上旬にそのチャンスがやってきました。
今回の一番の懸念材料は、長野市から白馬方面へのアクセス道路が、地すべりのため片側交互通行になっていて、通過にかなり時間がかかるということでした。行きにはここを通り抜けるのに20分を要しました。それでも計画していた時刻にはゴンドラに乗ることができました。

栂池とも迷ったのですが、栂池はロープウェイ、八方はゴンドラでのアクセスになるので、今回は八方にしました。平日なのでゴンドラには1人で乗れるだろうという目論見です。このコロナ禍の中、ロープウェイに他の誰かと同乗する勇気はありません。駐車場はすでに満車に近い状態ではありましたが、乗り場は空いていて、感染リスクが低いまま標高をあげることができました。

夏休みを今振り返ってみると、この日は山を歩くにはベストコンディションで、南の鹿島槍ヶ岳、五竜岳、北の白馬鑓ヶ岳、杓子岳、白馬岳方面は行動時間中ずっと見えていました。

遠見尾根方面をバックにしたオヤマソバです。花を楽しみたいところでしたが、時間は限られているので、午後12時半になったら八方池までたどり着けなくてもそこから引き返すつもりでどんどん歩きました。

でもこの花だけは見逃せません。今年も会えたハッポウタカネセンブリです。

とりあえずこれで今回の目的は果たせたと言ってもよかったのでした。

今まで注意していなかったこの花。家に帰って調べてみるとミヤマママコナのようです。漢字で書くと深山飯子菜で、花弁の中の白い部分をご飯粒に見立てているところから名前がついたっぽいです(別の説もあり)。

あとはおなじみの花々。

天気がいいので、青空を背景に取り入れて撮ってみたくなります。

行く手の唐松岳方面。扇の雪渓がきれいに見えていました。頂上山荘は営業休止ということで、テント泊のみ受け入れているということです。今でも脚力的には唐松岳日帰りだってできると思いますが、とにかく現状は時間との戦いです。

左のセリ科の花はなんとなく撮ってきたのですが、かろうじて写っている葉が、鋭く3裂しているところからタカネトウキとわかりました。右はヨツバシオガマとエゾシオガマ。

タカネマツムシソウ、ミヤマアキノキリンソウなど少し秋を感じさせる花も咲いていました(右下はキバナノカワラマツバ)。

カライトソウ、ウメバチソウ、イワイチョウ。

チングルマはもう綿毛。

引き返す時刻が迫る頃、八方池が見えてきました。つづきはこちら。
2021年8月おわり記
小さな湿原
ノアザミレストランの時とはまた別の場所です。

歩き始めはアサギマダラ。

多いとは思いませんが、どこに行ってもわりと見ることができているという印象です。

湿原に入ってアキアカネ。

風景が、秋を感じる色になってきました。

トリカブトなんてもう完全に秋の花です。

だいぶ傷んだ翅のウラギンヒョウモン。

ここでも会えたコヒョウモン。

鳥はウグイスとキジバト。キジバトはなぜかたくさんいました。湿原で何やら採食していたらしく、木道を歩いていくと次々に飛び立って針葉樹林の中に消えていきました。
2021年8月おわり記
ノアザミレストラン

標高的には亜高山帯の手前という感じの森です。

ベニヒカゲ。この青い縁取りのなんと美しいことでしょう。妖しいまでのコントラストです。

1頭だけ見たゴイシシジミ。今シーズンは見る機会があまりありません。

オオチャバネセセリ。こちらは逆に見る機会が多いです。

しばらく歩くと小さな湿原に出ました。今回の目的地はここです。

ここでもオオチャバネセセリ。

これはコチャバネセセリでいいでしょうか。名前は似てますが、全然違います。

アカタテハ。
ウラギンヒョウモン。こうしてみるとノアザミは偉大な蜜源です。

ハクサンフウロにはたぶんコヒョウモン。下の写真は別角度から。後翅裏だけみると私にはヒョウモンチョウっぽくも見えてしまうのですが、上のと同一個体です。前翅の丸みは確かによくわかります。難しい…。

さて再びノアザミに戻って。

これは初めて見る蛾です。調べてみると、シロシタオビエダシャクでよさそうです。

そしてキシタギンウワバ。ここで見たのは初めてです。
ここまで撮ったところでカメラの電池が切れまして、この他アサギマダラやヒメキマダラヒカゲ、モンキチョウなどもいましたが写真はなしです。
2021年8月おわり記
高原の花々

シャジクソウ。大ぶりなアカツメクサみたいに見えます。それもそのはず、アカツメクサもシロツメクサも同じマメ科シャジクソウ属です。でも日本在来のシャジクソウ属はこのシャジクソウだけで、しかも北海道と本州では長野・群馬・宮城くらいにしか見られない、分布の限られた花です。

ハクサンフウロ。

カワラナデシコ。

ノアザミ。

シモツケソウ。

シュロソウなど。

コウリンカなど。

マツムシソウなど。
2021年8月おわり記
高原の蛾
高原蝶を見に行くのつづきです。ミヤマモンキチョウも見ることができました。ほとんどとまることなく飛んでいたので写真は無理でした。
少し鳥も。

ビンズイ。

コガラ。このほか、ルリビタキ、ウグイス、メボソムシクイ、ヒガラ、ホシガラスを確認しました。

さて鱗翅に戻って、これはキシタギンウワバです。

以前と全く同じ場所で見ました。やっぱりここにいたのか!という感じでまさにピンポイント。3時間半歩いて見たのはここでだけです。

スモモエダシャク。7月に見たばかりだったので、覚えていました。

これは識別点がうまく写っていないのですが、ミスジシロエダシャクと考えてみます。

これは未同定。クロマメノキが写っています。これはミヤマモンキチョウの食草。一番最初に書いたミヤマモンキチョウの目撃地点はまさにここでした。

鱗翅の次は甲虫。一瞬ゴマダラカミキリかと思いました。調べてみるとシラフヒゲナガカミキリでよさそうです。標高の高い針葉樹林に生息するカミキリとのことです。

ウスユキソウにいたニンフホソハナカミキリ。この手の触角の先が白いカミキリの同定ポイントは先日覚えたばかりです。画像からは白い部分が2.5節あることがわかるのでニンフでいいと思います。

双翅目。青い紋を持つアブ!ということでとても印象的でした。この画像だけでは同定ができません。ヘリヒラタアブかマルヒラタアブのどちらかでよさそうで、その先に進むには顔の写真を撮っておく必要がありました。残念。

直翅目。ここまで来ると同定する元気がなくなってきます。ヒロバッタの仲間でいいでしょうか。

蜻蛉目はアキアカネ。
2021年8月おわり記
高原蝶を見に行く
この日の目当てはこのコヒョウモンです(ヒョウモンチョウかもしれません)。

ここでは見かける蝶の9割がこのコヒョウモンというすばらしさです。

ヒョウモンチョウとの区別は難しいのですが、こうしてみると前翅外縁の丸みがあるので、コヒョウモンとしてみました。

ただ、上の画像だと、向かって左の前肢外縁は丸く見えますが右は直線的に見えます。また、前翅の後ろの角にある2つの黒い紋が、つながる傾向にあるのはコヒョウモン、分離傾向にあるのがヒョウモンという記述が図鑑にあり、この写真に当てはめるとコヒョウモンということになりそうです。

他にもいろいろなひょうを見ることができました。これはギンボシヒョウモン。

そしてウラギンヒョウモンです。

数は少なかったですけれど、ベニヒカゲもいました。

アサギマダラ。

キアゲハ。

背中の青がやたら美しかったヒメキマダラヒカゲ。

ハクサンフウロで吸蜜していたクロヒカゲ。薄紫の縁取りがエモいです。

オオチャバネセセリ。

こちらはコチャバネセセリでいいと思います。
2021年8月おわり記