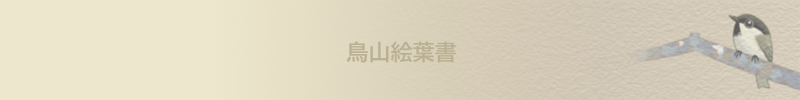野外手帳
-2021年2月
レンジャク観察記

「今季レンジャク4回目」の続きです。

ニコンZおじさんとはなんとなくそのままお別れして、一人で森の中を歩きました。

おじさんによると、午前中にも一人カメラマンが来ていたようです。鳥を見たり撮ったりしている人をここではこれまでに見たことがありませんが、それなりにここを観察フィールドとしている人はいるのでしょう。

レンジャクたちの行動パターンを見ていると、木の枝に止まって休んでいるように見える時間があり、地面に舞い降りて食べ物をついばんでいる時間がありと、メリハリがあるように感じました。また枝に止まっているときには大量に排泄しているシーンも何度か観察しました。ある程度食べると枝に上がり、消化が進むとまた採食行動に移るのではないかという感じでした。

比較的警戒心が弱いのもレンジャクの特徴と言っていいと思います。枝に止まっているときには、他の鳥に比べてかなり近づけます。とはいってもアップで撮れるほど寄れることはそれほどありません。

上の写真はかなり日が傾いてきてからの写真です。もうこの時間帯になれば採食はしないのかなと思ってみていたのですが、そんなことはなくて、この後再び地上でヤブランの実を食べていました。

毎シーズン会えるとは限らないレンジャクですから、この日はそれこそ飽きるほど見たり撮ったりしておきました。満足な一日でした。

2021年3月おわり記
今季レンジャク4回目

もう抜けてしまったかと思っていたのですが、逆に数が増えていました。

この場所では大変珍しいことなのですが、鳥を撮る人に会いました。ニコンのZにおそらく556をつけていて、服装は迷彩、かなり気合の入った人だなあと感じました。

ところが会話を交わしてみると、鳥を撮り始めたのは今年の1月になってからだそうで、それまではスポーツの写真を撮っていたとのことでした。で、「鳥でも撮ってみるか」という気持ちになったのだそうです。

鳥に関心を持つ人が増えることは歓迎すべきことなのですが、この鳥でも撮ってみるかという言い方はやっぱり気になってしまいます。野帳を被写体の一つとしてしか見ないカメラマンによるよろしくない話は、それこそ腐るほど目に、耳にしますから。

それでもこの方は、鳥を撮りはじめて日が浅いのに、鳥の名前はよくご存知でした。単なる撮影対象としてではなくて、野鳥の存在を大事に考えるカメラマンになっていただければと思いました。

さてレンジャクですけど、ヒキ合わせて50羽以上はいたと思います。ほとんどがヒレンジャクで、そこにキレンジャクが交じる感じでした。

シジュウカラやヤマガラがさえずり始めていて、風景はまだ冬の森のままではあるものの、春を感じた日でした。

その他には、メジロ、ウグイス、エナガ、コゲラ、ヒヨドリ、シロハラ、カケス、ハシボソガラスを確認しました。

2021年3月おわり記
探せども

今冬はアオシギには会えずじまいでした。ここは過去に観察したことがある場所で、何度か行ってみましたが空振りでした。

ただ3月になって、雪の残る湿原で見たことがあるので、この3月の休日の使い方次第では見るチャンスがまだあるかもしれません。
2021年3月おわり記
近隣池巡り
2月下旬の観察記録です。まず最初の池。

この池ではマガモが主。ついでコガモ。遠くにホシハジロ、ヒドリガモなどでした。
続いての池ではハシビロガモが見られるのが特徴的。次に多いのはコガモでした。

ハシビロガモはこれまであまり観察機会がありませんでしたが、昨春にこの池にハシビロがいることに気づき、今季もじっくり観察できました。ポイント開拓です。

最後の池は中学生の時から通っている場所。真冬はヒドリガモとオナガガモが多く、オカヨシガモがいることが特徴です。

カモたちの姿はだいぶ減って、特にオナガガモは数羽しか残っていませんでした。

そしてトモエガモがまだ残ってくれていました。

近かったオオバン、遠かったバン。
2021年3月なかごろ記
レンジャク三昧
三度レンジャク観察行。家から近い場所で観察できる幸せです。
最初に観察したのは幹に寄り添うメジロでした。

何をしているのだろうかと思いました。樹液をなめているのか、樹皮の奥に潜む虫を狙っているのか。

さてレンジャクはというと、前日より数を増やしていました。ヒレンジャクがほとんどで、そこにキレンジャクが混じっているという感じでした。

ヤブランの実の採食もたっぷり観察できました。

Twitterのレンジャク画像で、舌の形が独特だというのを知って、なんとか写真に残せないだろうかと思いましたが、ちょっと無理でした。

森の中を頻繁に飛び回り、あちこちの梢からから細い声が落ちてきます。

表題の通り、まさにレンジャク三昧となりました。



2021年3月なかごろ記
夕方のレンジャク
レンジャク見つけたの続きです。夕方になってもう一度行ってみることにしました。

木の枝に止まってしばらく休み、それからまた地面に舞い降りてヤブランの実をぱくぱく食べるということの繰り返しでした。糞をするシーンを何度か見ました。普通の鳥よりもたくさん食べてたくさん出すという印象です。

ヤブランの実を食べ尽くせばほかへと移動してしまうのでしょう。ここに食べるものがあるという情報をどうやって得て移動していくのか、とても興味深いです。
今回観察できている場所のすぐ近くでは、もう少し遅い時期に、ヤナギの若芽を菜食しているのを観察したことがあって、そこも自分のレンジャクポイントだったのですが、そのヤナギは昨年伐採されてしまったので、とても残念に思っています。

太陽がかなり傾いてきて、カメラのISOがどんどん上がってしまい(感度は自動制御に設定しています)、画像的にはやや苦しくなってしまいました。

でも午前に続いて午後も、たっぷりとレンジャクを見ることができていい一日でした。

2021年3月なかごろ記
レンジャク見つけた

いろいろバタバタしていて、これは2月中旬の記録です。

以前、「鳥を出す」という表現に噛み付いてしまって、TwitterのTLを荒らしてしまった苦い経験があるのですが、今回のレンジャクは「出した」と言ってもいいのかもしれません。
自分の観察範囲では毎年見られるわけではないレンジャク、でも来るとしたらこの場所のこの頃ですよねぇというのが自分の中にあって、前の週にもここに来てみました。その時は空振りだったのですが、今回はぴったり。まさに思い描いたようにレンジャクを見ることができました。

最初にキレンジャク、そしてヒレンジャクも。ヤブランの実を食べている様子も観察できました。合わせて10羽に満たない数でしたが、大満足。

ヤブランの実はメジロも利用していました。レンジャクは実を丸のみしていましたが、さすがにメジロのサイズだと果肉をついばむ感じでした。

メジロの他にはミヤマホオジロを観察。

あとジョウビタキ、シロハラ、ウソ、シジュウカラ、エナガ、ハシボソガラス、カケスも確認しました。

再びレンジャク観察。

この色、この形、本当にすばらしい鳥です。自然の造形の美しさ。

ずっと見ていたかったのですが、昼までには家に帰らなくてはなりません。

ぎりぎりまで観察を続け、気持ちを切り替えて帰宅しました。

家についてからもまだ心のなかに余韻が残っていました。よい鳥見ができました。

2021年3月なかごろ記
北へ帰る鳥と帰らない鳥
春のような日があったかと思えばまた雪が降り、でもやっぱりすぐ溶けるあたりが2月後半です。確実に春が近づいていることを感じる今日この頃。

畦道の道すがらにいつものツグミ。そろそろ北の地が恋しくなってきた頃でしょう。

川沿いにヒヨドリ。彼らは夏も残っていますが、秋に南下してきているはずなので、見かけるのは同じ個体ではないでしょう。この写真の彼?は、どこまで行くのやら。

それにしても改めてこうして見るとヒヨドリの渋い美しさにぞくっとします。

ベニマシコが姿を消した枯れたセイタカアワダチソウ群落にはホオジロが潜んでいました。カシラダカの姿が少ない今シーズンですが、ホオジロはいつもどおりです。彼らは居残り組かな。

ベニマシコを見なくなったと思ったら、この日はオスメスのペアを見つけました。前日の雪でまた戻ってきたとかでしょうか。オスはなかなか顔を見せてくれませんでした。もちろん彼らは北へ向かう鳥です。

ベニマシコを見つけたすぐ近くの田んぼにイカルの小群が降りていました。地面にいるのは珍しいなと思ったら、雪が溶けてできた水たまりで、水浴びをしていたのでした。この辺りでは夏場にイカルを見ることはあまりないように思います。冬が終われば標高の高いところへ移動していくイメージです。

その向こうの木立では、雪が残る山を背景にムクドリ。オレンジ色が鮮やかです。たぶん一年中この辺りで暮らす鳥です。

最後の写真はカワラヒワです。あまり亜種レベルの識別まで踏み込む気持ちはないのですが、カワラヒワも冬にはオオカワラヒワという北方系の亜種が南下してきているという話です。識別点は3列風切の白帯の太さらしいです。この画像を見る限り、白帯はわりと太く見えるので、これは亜種オオカラワヒワでいいのでしょう。たぶん。
2021年2月おわり記
春近し
春のような日でした。いつも接写に使うボディを、この間落としてしまい修理に出してあるので、第一線を退いていた600万画素の初代デジタル一眼レフにマイクロレンズを取り付けて、畦道を歩くことにしました。

オオイヌノフグリが土手一面に花を咲かせていました。帰化植物ですけど、これはいい花です。

冬を耐えたヒメオドリコソウ。

古い一眼レフですが、きちんと撮れるのはさすがです。コンデジだとこうはいかないでしょう。

ホトケノザ↑とナズナ↓。オオイヌノフグリやヒメオドリコソウと違って帰化植物ではないイメージなんですが、これらもどうも史前帰化植物らしいです。そうすると、農耕が始まる前の日本の春の野原にはどんな花が咲いていたのでしょう。

さえずりを始めているカワラヒワ。かなり好きな鳥の一つで、グリーンフィンチという英名はとてもかっこいい。でも印象的なのは緑より飛ぶと現れるイエローバンドですよね。

この冬はあまり見かけないアオジ。初夏の戸隠で早く彼らの歌声を聞きたいものです。

地上に降りているところを見かけることが多くなったツグミ。渡来直後の警戒心の強さは一体何なのでしょう(というか同じ種類で警戒心が時季によってどうしてこんなにも変わるものなのかという疑問です)。

畦道沿いの小さな林にはエナガの群れの姿がありました。

2021年2月おわり記
11年ぶりの池で雁見
クリオネの続きです。せっかく久しぶりに県外に出てきたからには、長野県にいてはなかなか見ることができない鳥を見て帰りたいものです。16時には自宅に帰らなければならない制約があるので、クリオネ展示の水族館から車でわずかの某池に寄りました。
この池での探鳥は、実に2009年12月以来です。周囲はかなりの雪で、水面も雪が浸っている感じでしたが、水面が見えている場所を見つけました。

車内に三脚を立てて観察開始です。11年前に来た時はミニバンに乗っていました。2列めを畳んで三脚を立て、3列目に座ってスライドドアを開ければ快適に観察ができました。今の車はヒンジドアですが、後席を片側だけたためば床に三脚を据え、シートに座って観察できるので、使い勝手はかなりいいです。
9割以上はマガモとオナガガモで占められていました。他にはホシハジロ、コガモ、カルガモ、トモエガモ、ヨシガモ、ミコアイサ、カワアイサを確認できました。
そし今回の一番の目的だったガン類も見ることができました。彼らがいる場所は非常に遠くて、、また天気のよさと気温の高さが災いして、陽炎がひどく、鮮明に見ることはできませんでしたが、時折近くに飛んできたり、またこの池に小群が飛来したりして、その時は双眼鏡でも十分に観察できました。

上の写真はヒシクイの群れですが、マガンも混じっています。下のようにマガンだけの群れも飛んでいました。ヒシクイは70羽以上、マガンは20羽くらいまでは数えましたが、このように時折出入りがありましたので、数はいい加減です。

長野県北部へのマガン飛来情報もありましたが、見に行く機会が作れなかず、残念な思いを抱いていたので、この日はとても満足できました。
2021年2月なかごろ記
クリオネを見に行った
隣県の水族館でクリオネを展示中ということで、ちょっと足を延ばしてみました。よく考えてみると、長野県を出たのは約4年ぶりでした。この1年はコロナ禍ということで、遠出をしなかった方も多いと思います。加えて介護となると、なかなか県境をまたぐ機会もなかったのでした。

水族館は空いていました。クリオネ(ハダカカメガイ)をゆっくり見ることができて満足です。混んでいたらこんな写真を撮るのもきっと顰蹙をかっていたと思われます。水槽に貼り付いて撮ることができました。

あとクラゲもよかったです。上からミズクラゲ、アマクサクラゲ、クシクラゲ、チチュウカイイボクラゲです。特にクシクラゲの虹色の輝きを見ることができたのはよかったです(あまりうまく撮れていなかったのがやや心残りです)。

あと、アオリイカがすてきでした。この水槽はクラゲを同じく、かなり長い時間見ていられる感じでした。

その他の非脊椎動物。クルマエビ、シロウミウシ、フウセンイソグンチャク、ミズダコ。

魚類ではゴンズイとマツカサウオが印象的でした。
2021年2月なかごろ記
少ない冬鳥
里山山麓で鳥探し。これまでにいろいろな冬鳥が出ている場所なんですけど、かなりの不発で、撮れたのもシロハラの後ろ姿だけです。

珍しい鳥を探しているわけではないのですが、アトリやシメなどいつも見られる種類も見る機会が少ない今冬は、やっぱりちょっと寂しいです。
2021年2月なかごろ記
ここで巴は今季3回目
トモエガモはまだいるかなと見に行ってみたら、♂2羽、♀1羽を確認できました。ずっとここに居着いていてくれているようです。ついでにアメヒも見つけました。

手前の藪にはルリビタキ、アオジとホオジロ。
2021年2月なかごろ記
鏡池では幸せでしたが

前回に続き、この日も鏡池まで来ました。ここではさすがに何人ものハイカーに会いました。

人がいなくなったのを見計らって短い動画を撮りました。
気温が高めだったので氷の上は早々に引き上げて、岸辺でチョコレートのおやつを食べました。

帰り道。

太陽が低くなってきて、雪原に伸びる影を楽しみながら歩くことにします。

今回は広角レンズをつけてきたのですが、影の青い縞の美しさを撮るなら中望遠程度の焦点距離がほしいところでした。
次は影の撮影を目当てに歩きに行こうと思ったのですが、これらの写真を撮ったカメラを落下させてしまいました。

帰宅し、デイバッグにカメラを入れた状態で車から降りたのですが、ジッパーが開いていて、アスファルトの上にカメラを落としてしまいました。
つけていた広角レンズは、鏡筒がマウントのところから割れてしまいました。ボディは外観に大きな傷はないものの、肩液晶の表示がおかしくなり、ファインダーが暗くなり、もちろんシャッターも切れません。

すぐに修理に出しました。後日見積もりが来まして、ボディは中古を買うより安い値段だったので(それでもかなり痛い金額でしたが)、直すことにしました。広角レンズは新品を買うよりも高い修理費用となってしまい(全損ってことですね…)、廃棄決定です。上の写真はこのレンズでの撮り納めとなってしまいました。
2021年2月なかごろ記
今季2度めのミズナラ大王
この記事の続きです。

ミズナラ大王は、もちろん私がつけた名前ではありません。この威容にはぴったりの名前です。

とりあえず木の周りをぐるっと一周。よく晴れた休日だったのでたくさんの人と会うことを覚悟していたのですが、中途半端な時間帯だったせいか、ここまで誰にも会わず、そしてミズナラ大王も独り占めでした。

ここで昼食です。とはいってもパンをかじるだけ。この木の迫力が良いおかずになります。今日は土曜日ですが母をデイサービスにお願いしてあるので、昼をまたいだ行動が可能な貴重な休日なのです

もう一度くらい来ようかなと思いました。3月になってしまえば、雪を乗せた姿は見られないかもですけれど。

随神門に到着。参道を横切り、再び森の中へ。

これまであまり歩いたことのない方面に足を向けてみました。

そこにもなかなかいい感じの木がありました。

鏡池の様子はこちら。
2021年2月なかごろ記
木に名前をつけて歩く

今季2度目の戸隠スノーシューです。今回は文句なしの晴天でした。

戸隠山に向かって雪原を行きます。暖かで、アウターなしのフリースだけで大丈夫。戸隠山からは時々小規模な雪崩の音が聞こえてきます。

セッケイカワゲラを発見。

とても暖かい日だったのですが、枝や幹に乗った雪がまだ付いている風景の中を歩けました。期待していなかったのでちょっとラッキーでした。
もう何度も歩いているので、勝手に名前をつけている木がいくつかあります。

これはヤドリギの木。この他にはこのあたりではヤドリギをくっつけている木はあまりありませんので、ちょっと目立ちます。

これはイボイボの木。どうしてこうなっちゃっているのかはわかりません。これと似た木は他にはないので、これも結構目立ちます。

これは名付けて豪腕の木。ぐいんと手前に伸びた枝が印象的です。近年枯れ枝がもたれかかっていて、この豪腕が折れてしまうのではないかと心配です。

実際、こういう木もありますから。続きはこちら。
2021年2月なかごろ記